ブログ
痛みがないのに歯磨き後に歯ぐきから血が出たり腫れたりする。 これは歯周病なの?

歯磨きのたびに歯ぐきから血が出るけれど、特に痛みはない。そんな経験を「いつものこと」だと見過ごしていませんか?実は、その「痛みがない」という状態こそ、あなたの歯を失う危険が静かに進行している、最も注意すべきサインかもしれません。
歯周病は「サイレント・ディジーズ(静かなる病気)」と呼ばれ、厚生労働省の調査では成人の約8割が罹患しているという、もはや国民病とも言える病気です。痛みという明確な警告がないために放置されやすく、気づいた時には歯を支える大切な骨が溶け、手遅れになっているケースも少なくありません。
この記事では、見逃しがちな歯周病の初期症状から、ご自身でできる危険度チェック、そして放置した場合の深刻なリスクまでを詳しく解説します。あなたの大切な歯を生涯守るために、まずはご自身の状態を正しく知ることから始めませんか。
痛みがないのは要注意?歯周病の初期症状とセルフチェック法5つ
歯磨きのたびに歯ぐきから血が出るけれど、特に痛みはないからと、ついそのままにしていませんか。実は、その「痛みがない」という状態こそが、歯周病が静かに進行している危険なサインかもしれません。
歯周病は初期段階では自覚症状がほとんどなく、歯科医療の現場では「サイレント・ディジーズ(静かなる病気)」とも呼ばれています。厚生労働省の調査では、成人の約8割が何らかの歯周病にかかっていると報告されています。
痛みという分かりやすい警告がないため、気づいた時には手遅れで、歯を支える骨が大きく失われていることも少なくありません。ご自身の歯ぐきの状態を正しく知り、早期発見につなげることが何よりも大切です。ここでは、歯周病の初期症状とご自身で確認できるチェック方法を詳しく解説します。

歯ぐきからの出血や腫れは歯肉炎のサイン
歯磨きのときに出血したり、歯ぐきが少し腫れぼったく感じたりするのは、「歯肉炎(しにくえん)」の代表的なサインです。歯肉炎は歯周病の初期段階にあたり、歯周病への入り口と言えます。
これは、歯と歯ぐきの境目に残った歯垢(プラーク)に含まれる細菌が原因です。細菌が出す毒素に対して、私たちの体が防御反応を起こし、歯ぐきに炎症が生じるのです。
歯肉炎の主な症状
- 歯磨き時の出血 歯ブラシやデンタルフロスを使った後に、唾液に血が混じります。
- 歯ぐきの色の変化 健康的なピンク色ではなく、炎症により赤みを帯びてきます。
- 歯ぐきの腫れ 歯と歯の間の歯ぐきが丸みを帯び、腫れぼったい感じがします。
- 歯ぐきの違和感 痛みはなくても、むずがゆさを感じることがあります。
幸いなことに、歯肉炎の段階であれば、炎症は歯ぐきだけにとどまっています。そのため、歯科医院で専門的なクリーニングを受け、毎日の丁寧なセルフケアで原因である歯垢をしっかり取り除けば、健康な状態に戻せる可能性が高いのが特徴です。
出血を恐れて歯磨きを避けてしまうと、歯垢がさらに蓄積し、症状は悪化の一途をたどります。このサインを決して見逃さず、適切なケアを始めることが重要です。
歯周病と歯肉炎の決定的な違い
「歯肉炎」と「歯周病」は、しばしば同じように使われますが、医学的には明確な違いがあります。その決定的な違いは、「歯を支える骨(歯槽骨:しそうこつ)が破壊されているかどうか」です。
歯肉炎は歯周病の一歩手前の状態であり、両者の違いを理解しておくことが、お口の健康を守るうえで非常に重要になります。
| 項目 | 歯肉炎(可逆的) | 歯周病(歯周炎)(不可逆的) |
|---|---|---|
| 炎症の範囲 | 歯ぐき(歯肉)に限定 | 歯ぐきに加え、歯根膜、セメント質、歯槽骨など歯を支える組織全体 |
| 歯槽骨への影響 | 破壊されていない | 破壊され、溶かされている |
| 回復の可能性 | 適切なケアで、元の健康な状態に戻せる可能性がある | 一度破壊された歯槽骨は、基本的には元の状態には戻らない |
歯肉炎は、いわば「可逆的(元に戻れる)」な状態です。しかし、これが進行して歯周病(専門的には歯周炎)になると、炎症は歯ぐきの奥深くへと広がり、歯を支える土台である歯槽骨を溶かし始めます。
一度失われた歯槽骨は、現在の医療技術では完全に元通りにすることは非常に困難です。つまり、歯周病は「不可逆的(元に戻れない)」な状態なのです。骨の破壊が進むと歯がグラグラし、最終的には歯が抜け落ちる原因となります。
なぜ歯周病の初期は痛みを感じにくいのか
虫歯であれば「冷たいものがしみる」「ズキズキ痛む」といったはっきりとした痛みを感じることが多いのに、なぜ歯周病は初期に痛みを感じにくいのでしょうか。これには、主に3つの理由があります。
- 歯槽骨には痛みを感じる神経が少ない 歯周病によって破壊される歯槽骨(歯を支える顎の骨)には、痛みを感じる神経がほとんど分布していません。歯の内部にある歯髄(しずい)のように痛みを感じる神経が豊富な組織とは異なり、骨が静かに溶けても、痛みとして脳に信号が送られにくいのです。
- ゆっくり進行する「慢性炎症」だから ケガをしたときのような急激な炎症(急性炎症)は強い痛みを伴います。一方、歯周病は数ヶ月から数年という長い年月をかけてゆっくりと進行する「慢性炎症」です。そのため、激しい痛みではなく、「歯ぐきが腫れぼったい」「むずがゆい」といった、見過ごされがちな弱い症状が中心となります。
- 歯の神経に直接影響しない 虫歯は歯そのものを溶かし、神経に近づくにつれて痛みが強くなります。それに対して、歯周病は歯の周りの組織の病気です。初期段階では歯の神経に直接的な影響が及ばないため、痛みが出にくいのです。
これらの理由から、「痛みがないから大丈夫」という自己判断は非常に危険です。痛みや歯の揺れといった自覚症状が出たときには、歯周病がかなり進行してしまっているケースも少なくありません。
口臭・歯が長くなった・歯ぐきの色の変化
歯ぐきからの出血や腫れ以外にも、歯周病のサインは日常生活の中に隠れています。特に注意したいのが、「口臭」「歯の見た目の変化」「歯ぐきの色」の3つです。
- 口臭 歯周病菌は、お口の中のタンパク質(血液の成分や剥がれ落ちた細胞など)を分解する際に、揮発性硫黄化合物という強い臭いを放つガスを発生させます。これが歯周病による口臭の主な原因です。丁寧に歯を磨いても口臭が気になる場合は、歯周病の可能性があります。
- 歯が長くなったように見える 歯周病が進行すると、炎症によって歯ぐきが下がり始めます(歯肉退縮)。すると、本来は歯ぐきに隠れていた歯の根の部分が露出するため、鏡で見たときに「以前より歯が長くなった」ように感じられます。これは、歯を支える土台が失われつつある危険なサインです。
- 歯ぐきの色の変化 健康な歯ぐきは、引き締まった薄いピンク色(コーラルピンク)をしています。一方、歯肉炎や歯周病にかかると、炎症によってうっ血し、赤色や赤紫色に変化します。また、触るとブヨブヨと柔らかい感触になります。毎日の歯磨きの際に、歯だけでなく歯ぐきの色や形もチェックする習慣をつけましょう。
自分でできる歯周病危険度チェックリスト
ご自身の歯ぐきの状態が気になる方は、以下のリストでセルフチェックをしてみましょう。当てはまる項目が多いほど、歯周病のリスクが高い、あるいはすでに進行している可能性があります。
【歯周病危険度チェックリスト】
- □ 歯磨きのとき、歯ブラシに血がつくことがある
- □ 歯ぐきが赤く腫れていたり、ブヨブヨしていたりする
- □ 朝起きたときに、口の中がネバネバする感じがする
- □ 口の臭いが気になる、または人から指摘されたことがある
- □ 歯と歯の間に食べ物が挟まりやすくなった
- □ 以前に比べて歯が長くなったように見える
- □ 歯ぐきを押すと、白い膿のようなものが出ることがある
- □ 指で押すと少しグラグラする歯がある
- □ 歯ぐきがむずがゆい、または違和感がある
- □ 喫煙している
早期発見・早期治療が、あなたの大切な歯を未来まで守ることにつながります。
歯周病を放置する3つのリスクと全身疾患との怖い関係
「歯磨きで少し血が出るくらい」「特に痛みがないから大丈夫だろう」そう考えて、歯ぐきからの小さなサインを見過ごしてはいませんか。
実は、歯周病はお口の中だけの問題では済みません。痛みなく進行し、気づいたときには歯を失うだけでなく、全身の健康に深刻な影響を及ぼすことが近年の研究で明らかになっています。
ここでは、歯科医師の視点から、歯周病を放置することの3つの大きなリスクと、全身の病気との怖い関係について、具体的に解説していきます。

歯を支える骨が溶けて歯が抜ける
歯周病がもたらす最も深刻なリスクは、歯を支える顎の骨(歯槽骨:しそうこつ)が静かに溶けてしまうことです。
私たちの歯は、歯槽骨という土台にしっかりと根を張っています。しかし、歯周病が進行すると、歯周病菌が出す毒素や、それに対抗しようとする体の免疫反応によって、この骨が少しずつ破壊されていきます。
歯が抜けるまでの静かなプロセス
- 歯周ポケットの形成 歯と歯ぐきの間の溝が深くなり、歯周病菌の温床となります。
- 歯槽骨の破壊 歯周ポケットの奥深くで炎症が続き、歯槽骨が溶け始めます。歯槽骨には痛みを感じる神経が乏しいため、この段階でも強い痛みはほとんどありません。
- 歯の動揺 土台である骨を失った歯は、次第にグラグラと揺れ始めます。この頃になると「硬いものが噛みにくい」といった自覚症状が出始めます。
- 歯の脱落 最終的には、食事中などに自然に抜け落ちてしまったり、重度の歯周病と診断され抜歯せざるを得なくなったりします。
重要なのは、一度溶けてしまった歯槽骨は、現在の医療技術で完全に元の状態に戻すことは極めて困難であるという点です。大切な歯を生涯にわたって守るためには、骨が溶け始める前の初期段階で治療を開始することが不可欠です。
歯周病菌が全身へ及ぼす影響(糖尿病・心疾患・誤嚥性肺炎)
歯周病は、お口の中だけの病気と考えるのは大きな間違いです。炎症を起こした歯ぐきの血管から歯周病菌や菌が産生する炎症物質が血液中に入り込み、全身を巡ることで、さまざまな病気のリスクを高めます。
| 関連が指摘される全身疾患 | 歯周病との関係性 |
|---|---|
| 糖尿病 | 歯周病は「糖尿病の第6の合併症」とも呼ばれています。歯周病菌が出す物質が、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げるため、血糖コントロールが悪化しやすくなります。逆に糖尿病の方は免疫力が低下し、歯周病が悪化しやすいという負の連鎖に陥ることがあります。 |
| 心疾患・脳血管疾患 | 血液中に入った歯周病菌が血管の壁に付着し、動脈硬化を促進することが分かっています。動脈硬化が進行すると血管が狭くなり、心筋梗塞や脳梗塞といった命に関わる病気を引き起こすリスクが高まります。 |
| 誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん) | 食べ物や唾液が誤って気管に入ってしまうことを誤嚥(ごえん)と言います。お口の中に歯周病菌が多いと、唾液と共に菌が肺に流れ込み、肺炎を起こすリスクが高まります。特に飲み込む力が低下したご高齢の方では、命取りになることもある危険な病気です。 |
これらは、歯周病と全身疾患との関連性の一例に過ぎません。お口のケアを徹底することは、ご自身の全身の健康を守るための重要な生活習慣なのです。
妊娠中の歯周病が早産・低体重児出産のリスクを高める
妊娠を計画されている方や、現在妊娠中の方は、特に歯周病に注意が必要です。妊娠中は、女性ホルモンのバランスの変化により、特定の歯周病菌が活発になったり、歯ぐきの炎症が起きやすくなったりします。
これを「妊娠性歯肉炎」と呼び、つわりで歯磨きが十分にできないことや、食事の回数が増えることも症状を悪化させる一因です。
妊娠中の歯周病がお腹の赤ちゃんに及ぼす影響は深刻です。歯周病によって産生される炎症物質の一部は、子宮の収縮を促す作用を持っています。この物質が血流に乗って子宮に達すると、正規の時期より早く陣痛を誘発し、早産や低体重児(2,500g未満)出産のリスクを高めることが多くの研究で報告されています。
そのリスクは、喫煙やアルコール摂取による影響と同程度か、それ以上とも言われています。生まれてくる赤ちゃんのためにも、体調が安定している妊娠中期に一度、歯科検診を受けることを強くお勧めします。
家族にうつる?キスや食器共有で起こる歯周病菌の感染
「歯周病は人にうつりますか?」これは、私たちが診療の現場で非常によく受ける質問の一つです。
結論から言うと、歯周病そのものが風邪のようにうつるわけではありません。しかし、その原因となる「歯周病菌」は、唾液を介して人から人へと感染する可能性があります。
【主な感染経路】
- 夫婦やパートナーとのキス
- 親子での食器(スプーン、箸など)やコップの共有
- 食べ物の口移し
特に、生まれたばかりの赤ちゃんの口の中には、歯周病菌は存在しません。多くの場合、ご両親をはじめとする身近な大人から、スキンシップなどを通して唾液を介して感染すると考えられています。
もちろん、歯周病菌が口の中に感染したからといって、誰もがすぐに歯周病を発症するわけではありません。その後の歯磨きの習慣や、個人の免疫力、生活習慣などが大きく関わってきます。
しかし、ご自身の口の中の歯周病菌を減らすことは、感染のリスクを減らす上で最も効果的な対策です。歯科医院で適切な治療を受けることは、ご自身の健康のためだけでなく、大切なご家族、特に小さなお子さんの将来の健康を守ることにも直結するのです。
歯周病の基本的な治療法と今日からできる予防ケア4選
歯ぐきからの出血や腫れといったサインに気づき、「もしかして歯周病かもしれない」と不安に感じている方もいらっしゃるでしょう。
歯周病は自覚症状が少ないまま進行しますが、早期に適切な治療とケアを始めれば、その進行を食い止め、大切な歯を守ることが可能です。
歯周病治療の成功は、次の2つの柱にかかっています。
- 歯科医院で行うプロフェッショナルケア 歯周病の原因となる歯石などを専門的に除去します。
- ご自身で行うセルフケア 日々の歯垢(プラーク)コントロールで、再発を防ぎます。
この両輪がうまく噛み合ってこそ、お口の健康を取り戻し、維持することができます。ここでは、具体的な治療法と今日からすぐに始められる予防ケアについて、詳しく解説していきます。

歯科医院で行う歯石除去(スケーリング)とSRP
歯周病治療の根幹は、その原因である歯垢と、歯垢が石灰化して硬くなった歯石を徹底的に取り除くことです。歯垢は毎日の歯磨きで落とせますが、一度こびりついた歯石はご自身のケアでは除去できません。
そのため、歯科医院での専門的な器具を使ったクリーニングが不可欠となります。
| 治療法 | スケーリング | SRP(スケーリング・ルートプレーニング) |
|---|---|---|
| 主な目的 | 歯の表面や歯ぐきの縁に見える歯石の除去 | 歯周ポケットの奥深く、歯根に付着した歯石や汚染物質の除去 |
| 対象 | 比較的軽度な歯肉炎〜歯周炎 | 中等度以上に進行した歯周炎 |
| 処置する場所 | 歯ぐきの上(縁上:えんじょう) | 歯ぐきの下(縁下:えんか) |
| 麻酔の必要性 | 通常は不要 | 痛みを伴うことが多いため、局所麻酔を使用することがある |
- スケーリング(歯石除去) 「スケーラー」という専用の器具(超音波で歯石を振動で砕く器具や、手用の器具)を使い、歯の表面や歯ぐきの境目についている歯石や歯垢を丁寧に取り除く処置です。これは、歯周病治療の最初のステップとなります。
- SRP(スケーリング・ルートプレーニング) 歯周病が進行すると、歯と歯ぐきの間の溝(歯周ポケット)が深くなり、歯を支える歯根(ルート)の表面にまで歯石が付着します。SRPは、この歯周ポケットの奥深くにある歯石や、細菌の毒素に汚染された歯根の表層を滑らかに(プレーニング)する治療です。 歯根の表面をツルツルにすることで、歯垢が再び付着しにくい環境を整え、歯ぐきの炎症の改善と再付着の予防を目的とします。SRPは歯ぐきの中を処置するため、痛みを感じることがあります。その際は麻酔を使用しますのでご安心ください。
これらの処置は、いわば歯周病という家の「大掃除」です。まずは専門家が徹底的に汚れを取り除き、クリーンな状態にリセットすることが治療の始まりとなります。
正しい歯磨き(ブラッシング)とデンタルフロスの使い方
歯科医院での治療効果を長持ちさせ、歯周病の再発を防ぐためには、毎日のセルフケアの質を高めることが何よりも重要です。
歯科医院でのプロケアが「大掃除」なら、セルフケアは「日々の掃除」です。この日々の掃除を怠れば、お口の中はすぐに汚れてしまいます。「磨いている」と「磨けている」は違うということを意識しましょう。
- 正しい歯磨きのポイント
- 歯ブラシの選択 ヘッドが小さく、毛の硬さは「ふつう」が基本です。歯ぐきが弱っている場合は「やわらかめ」を選びましょう。
- 当て方 歯周ポケットを清掃するため、歯と歯ぐきの境目に毛先を45度の角度で優しく当てます。
- 動かし方 鉛筆を持つように軽く握り、5〜10mm程度の幅で小刻みに振動させるように動かします。ゴシゴシと強い力で磨くと、歯ぐきを傷つける原因になります。
- 磨く順番 磨き残しを防ぐため、「右上の奥歯の外側から前歯へ」のように、ご自身で磨く順番を決めておくと効果的です。
- デンタルフロスの使い方 歯ブラシだけでは、歯と歯の間の汚れは約6割しか落とせません。歯周病は歯と歯の間から進行しやすいため、デンタルフロスの使用は必須です。
- 長さ 約40cm(指先から肘くらい)の長さにフロスを切ります。
- 持ち方 両手の中指に巻きつけ、指の間が10〜15cmになるように張ります。
- 挿入 親指と人差し指でフロスをつまみ、歯と歯の間にゆっくりと、のこぎりを引くように挿入します。決して力任せに押し込まないでください。
- 清掃 歯の側面に沿わせ、「C」の字を描くように巻きつけ、歯ぐきの溝の少し中まで入れ、上下に数回動かして汚れをかき出します。
毎日の習慣にするのは大変に感じるかもしれませんが、正しいケアは将来、歯を失うリスクを大幅に減らしてくれます。
歯周病予防に効果的な歯磨き粉や洗口液の選び方
歯磨き粉や洗口液(マウスウォッシュ)は、正しいブラッシングを補助する役割として非常に有効です。歯周病予防を目的とする場合は、配合されている薬用成分に注目して選びましょう。
アルコールを含む製品は強い爽快感が得られますが、刺激が苦手な方やお口が乾燥しやすい方は、ノンアルコールタイプがおすすめです。
どの製品がご自身の状態に合っているか迷った場合は、自己判断で選ぶ前に、かかりつけの歯科医師や歯科衛生士に相談するのが最も確実です。あなたのお口の状態に最適なケア用品を提案してくれるはずです。
まとめ
今回は、痛みがない歯ぐきの出血や腫れが、実は歯周病の危険なサインである理由とそのリスクについてご紹介しました。
歯周病は「サイレント・ディジーズ」と呼ばれ、痛みなどの自覚症状がないまま静かに進行し、気づいたときには歯を支える骨を溶かしてしまう怖い病気です。さらに、お口の中だけでなく、糖尿病や心疾患といった全身の健康にも影響を及ぼすことが分かっています。
しかし、出血や腫れといった初期のサインの段階であれば、適切なケアで健康な状態に戻せる可能性が高いのも事実です。セルフチェックで一つでも当てはまった方、少しでも不安に感じた方は、自己判断で放置せず、ぜひお近くの歯科医院へ相談してみてください。それが、あなたの大切な歯と全身の健康を守るための、最も確実な第一歩になります。
監修者情報
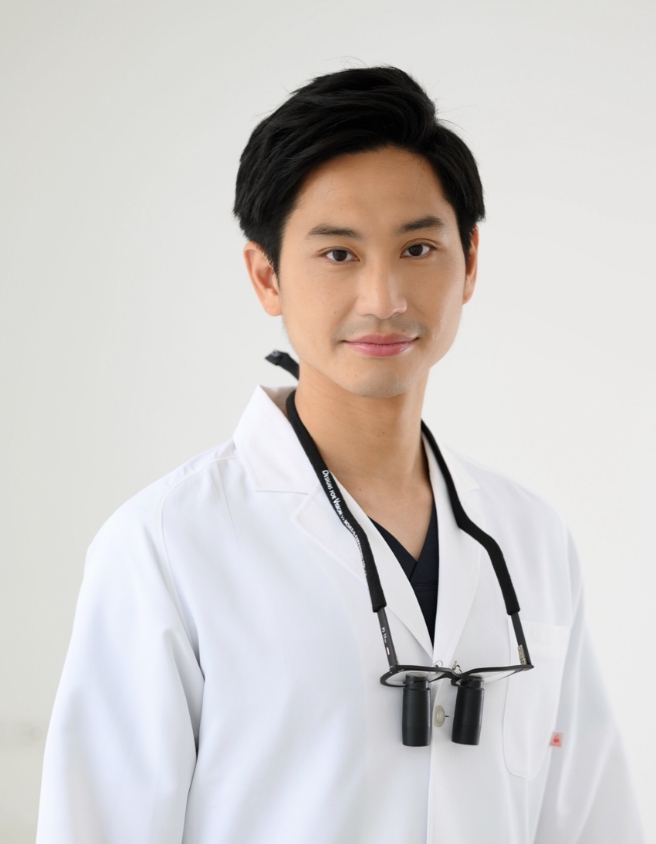
牧野歯科・矯正歯科 歯科医師
牧野 盛太郎Seitaro Makino
略歴
所属学会
- 日本口腔外科学会認定医
- 日本再生医療学会認定医
- 日本口腔外科学会
- 日本再生医療学会
- 日本顎顔面インプラント学会
- 日本口腔インプラント学会