ブログ
歯周病患者の矯正治療のリスク
「歯並びはきれいにしたいけれど、歯周病があるから矯正は無理かもしれない…」と、治療を諦めかけていませんか?実は、その不安は正しく、歯周病を管理しないまま矯正を始めると、歯周組織の破壊が加速し、最悪の場合、歯が抜け落ちてしまうといった深刻な事態を招く可能性があります。
歯周病患者さんの矯正治療に潜む具体的なリスクと治療を成功に導くための必須条件を解説します。
歯周病の矯正治療に潜む4つのリスク
歯並びをきれいにしたいと考えていても、歯周病があると「矯正治療はできないのでは?」と不安に感じてしまうかもしれません。たしかに、歯周病を抱えたまま矯正治療を始めると、いくつかのリスクが伴います。しかし、リスクを正しく理解し、適切な手順を踏むことで、安全に治療を進めることは可能です。ここでは、歯周病の方が矯正治療を受ける際に考えられる4つのリスクについて、わかりやすく解説します。
歯周組織の炎症が悪化し歯が抜け落ちる可能性
歯周病の最も大きな問題は、歯ぐきや歯を支える骨(歯槽骨)に炎症が起きていることです。矯正治療は、歯に力を加えて骨の中を少しずつ移動させる治療法です。このとき、骨では「吸収(骨が溶ける)」と「再生(骨ができる)」が繰り返されます。
もし、歯周病による炎症が残ったまま矯正治療を始めてしまうと、歯を動かす力が炎症をさらに悪化させてしまうことがあります。ある研究でも、歯周炎が十分にコントロールされていない状態で矯正治療を行うと、歯周組織の破壊が加速する可能性があると報告されています。
【炎症が悪化する仕組み】
- 歯周病の状態
- 歯ぐきに炎症があり、歯を支える骨が弱っています。
- 矯正力の負荷
- 矯正装置によって歯に力が加わります。
- 炎症の増悪
- 力が加わることで、もともとあった炎症がさらに強くなります。
- 骨吸収の加速
- 炎症によって、歯を支える骨が通常より速いスピードで溶けてしまいます。
この状態が続くと、歯を支えきれなくなり、歯がぐらぐらして、最悪の場合は抜け落ちてしまう危険性があります。そのため、矯正治療を始める前には、必ず歯周病の治療を優先し、炎症をしっかりと抑えることが不可欠です。
歯槽骨の吸収が加速し歯肉が下がる(歯肉退縮)
歯肉退縮(しにくたいしゅく)とは、歯ぐきが下がってしまい、これまで隠れていた歯の根っこ部分が見えてくる状態のことです。歯周病が進行すると、歯を支える歯槽骨が溶かされてしまうため、それに伴って歯ぐきも下がっていきます。
矯正治療では、歯を動かす過程で歯槽骨の形が変わります。特に、歯を外側に動かすような力を加えた場合、歯を覆う骨が薄くなりやすく、歯肉退縮が起こる可能性があります。歯周病によってすでに歯槽骨が少なくなっている方は、健康な方に比べてこのリスクがさらに高まります。
【歯肉退縮によって起こりうること】
- 見た目の問題
- 歯が長く見えたり、歯と歯の間のすき間(ブラックトライアングル)が目立ったりします。
- 知覚過敏
- 歯の根っこは刺激に弱いため、冷たいものや熱いものがしみやすくなります。
- 虫歯のリスク
- 露出した歯の根はエナメル質に覆われていないため、虫歯になりやすいです。
歯周組織が減少した状態での矯正治療は、より慎重な治療計画が求められます。歯を動かす方向や力の加え方を緻密にコントロールし、歯肉退縮のリスクを最小限に抑えることが重要です。
矯正装置による清掃不良で歯周病が再発・進行
矯正治療中は、お口の中に装置が入るため、どうしても歯磨きがしにくくなります。特に、歯の表面にブラケットやワイヤーを固定するタイプの矯正装置は、食べかすや歯垢(プラーク)がたまりやすい複雑な構造をしています。
磨き残した歯垢は、歯周病菌のすみかとなります。せっかく治療で歯周病を改善させても、矯正中の清掃が不十分だと、歯周病が再発したり、さらに進行してしまったりするのです。
研究によると、取り外し可能なマウスピース型矯正装置(クリアアライナー)は、ワイヤー矯正に比べて口内環境の乱れを引き起こす特定の細菌の増殖が少ない傾向にあると報告されています。口内環境の乱れとは、お口の中の細菌バランスが崩れること(ディスバイオシス)を指します。
しかし、マウスピース型矯正装置であっても、装置自体の洗浄を怠ったり、装着したまま糖分のある飲み物を飲んだりすると、細菌が増殖しリスクとなります。
| 矯正装置の種類 | 清掃のしやすさ | 歯周病リスクのポイント |
|---|---|---|
| ワイヤー矯正 | 難しい | ブラケットやワイヤーの周りに歯垢がたまりやすいです。 歯間ブラシやタフトブラシなど補助的な清掃用具が必須です。 |
| マウスピース矯正 | やや易しい | 取り外して歯磨きができるため衛生的です。 ただし、装置の洗浄を怠ると細菌の温床になる可能性があります。 |
どちらの装置を選ぶにしても、毎日の丁寧なセルフケアと、歯科医院での定期的な専門的クリーニングが欠かせません。
過度な矯正力による歯根吸収(歯の根が短くなる)
歯根吸収(しこんきゅうしゅう)とは、矯正治療で歯に力がかかることによって、歯の根っこ(歯根)の先が少しずつ溶けて短くなってしまう現象です。これは、矯正治療を受けるすべての人に起こりうるリスクですが、歯周病の方は特に注意が必要です。
歯周病で歯を支える骨が少なくなっていると、健康な歯に比べて、同じ力を加えても歯根にかかる負担が大きくなります。その結果、歯根吸収が起こるリスクが高まるのです。歯根が著しく短くなると、歯を支える力が弱まり、将来的に歯が抜けやすくなるなど、歯の寿命に影響を及ぼす可能性があります。
【歯根吸収のリスクを減らすために】
- 適切な力加減
- 研究でも、歯根吸収のリスクを最小限に抑えるためには、弱い力をかけてゆっくりと歯を動かすことが推奨されています。
- 精密な検査
- 治療開始前にレントゲンや歯科用CTで歯根の状態を正確に把握し、リスクを評価します。
- 定期的なモニタリング
- 治療中も定期的にレントゲン撮影を行い、歯根に異常が起きていないかを確認します。
歯周病を抱える方の矯正治療では、特にこの力のコントロールが重要になります。経験豊富な歯科医師のもとで、歯と歯周組織に負担の少ない、丁寧な治療計画を立ててもらうことが大切です。
矯正治療を安全に進めるための3つの必須条件
歯周病があると矯正治療のリスクはありますが、いくつかの重要な条件を満たせば治療を進めることが可能です。
条件1:矯正開始前の徹底した歯周基本治療とプラークコントロール
矯正治療という「家(歯並び)」を建てる前に、 まずは「土地(歯ぐきや骨)」の状態を整える必要があります。 これが、歯周基本治療とプラークコントロールです。
歯周病は、歯ぐきや歯を支える骨に炎症が起きている状態です。 この炎症が残ったまま歯を動かすと、病状を悪化させてしまい、 歯を支える土台をさらに失うことになりかねません。
ある研究では、歯周病の炎症が管理されていない状態で、 歯を骨に沈み込ませる(圧下)ような力を加えると、 歯周組織の破壊が進む可能性が指摘されています。
そのため、矯正治療を始める前には、 必ず歯周病の治療を優先することが大原則となります。
【具体的な歯周基本治療の内容】
- 歯垢・歯石の除去 歯周病の直接的な原因である歯垢や歯石を、専門の器具を使ってきれいに取り除きます。 歯の表面だけでなく、歯周ポケットの奥深くも清掃します。
- PMTC(専門的機械的歯面清掃) 歯科医師や歯科衛生士が、専用の機器とペーストを使い、毎日の歯磨きでは落とせない汚れを除去する処置です。
- ブラッシング指導(プラークコントロール)治療の成功には、ご自身による日々のケアが不可欠です。 お口の状態に合わせた正しい歯磨きの方法を身につけ、ご自身で歯垢をしっかり管理できるようにします。
歯周病の状態によっては、歯周外科治療や骨を再生させる治療が追加で必要になることもあります。 まずは土台を万全に整えることが、安全な矯正への第一歩です。
条件2:CBCT(歯科用CT)による精密な骨レベルの診断
安全な治療計画を立てるには、歯を支える骨の状態を、 正確に知ることが欠かせません。 そこで活躍するのが、CBCT(歯科用CT)です。
通常のレントゲンは二次元の平面的な画像ですが、 CBCTは三次元の立体的な画像で、お口の中を撮影できます。 これにより、目では見えない部分を詳細に把握できます。
CBCTを用いることで、歯科疾患の診断精度は大幅に向上し、 より正確な治療計画を立てられると研究でも報告されています。 歯周病の方の矯正では、特にその情報が重要になります。
【CBCTでわかること】
- 歯を支える骨の厚み、高さ、密度
- 歯の根っこの正確な長さや形、位置関係
- 骨が吸収されて薄くなっている部分の特定
これらの詳細な情報をもとに、歯をどの方向へ、 どれくらい動かせるのかをシミュレーションします。 骨が薄い部分を避けるなど、リスクの少ない安全な計画を、 ミリ単位で立てることが可能になるのです。
もちろん、CBCTにはコストがかかることや、 従来のレントゲンよりは放射線の量が多いという側面もあります。 しかし、得られる情報の価値は非常に高く、 安全な治療のためには利益が上回る場合が多い検査です。
条件3:歯周組織に配慮した適切な矯正力の緻密なコントロール
歯周病を経験した歯や歯ぐきは、とてもデリケートです。 そのため、歯を動かす際には、非常に弱く、 そして緻密な力のコントロールが求められます。
矯正治療は、歯に力をかけて骨の代謝(吸収と再生)を促し、 少しずつ歯を動かしていく仕組みです。 しかし、弱った組織に強い力をかけるのは禁物です。
過度な力は、歯を支える骨の吸収を過剰に進めたり、 歯の根が短くなる「歯根吸収」のリスクを高めたりします。 研究でも、歯根吸収のリスクを最小限に抑えるためには、 「軽い力」でゆっくり歯を動かすことが推奨されています。
重要なのは、歯周病の炎症がしっかりと抑えられていることです。 炎症さえなければ、歯を骨の中に沈み込ませる「圧下」の動きも、 歯周組織にさらなる破壊を起こしにくいことがわかっています。
装置別の清掃性の違い
矯正装置には、大きく分けて2つのタイプがあります。 歯に直接固定する「ワイヤー矯正」と、取り外し可能な「マウスピース矯正」です。 歯周病がある場合、この選択がお口のケアのしやすさを大きく左右します。
ワイヤー矯正は、装置が複雑で歯磨きが難しくなるのが課題です。 一方、マウスピース矯正は取り外して歯を磨けるため、衛生的です。 近年の研究では、この清掃性の違いが、お口の中の細菌環境に、 どのような影響を与えるかが明らかになってきました。
ある系統的レビューによると、マウスピース矯正の方が、 ワイヤー矯正に比べてお口の中の細菌バランスの乱れ、 いわゆる「ディスバイオシス」が少ない傾向にあると報告されています。
ディスバイオシスとは、お口の中の悪玉菌が増え、 良い働きをする菌とのバランスが崩れてしまう状態のことです。 このバランスの乱れは、歯周病だけでなく、 全身の炎症などにも関わると考えられています。
| 矯正方法 | 清掃のしやすさとリスク | 医師からのアドバイス |
|---|---|---|
| ワイヤー矯正 | ・装置の周りに歯垢がたまりやすく、清掃が難しいです。 ・歯周病の再発や進行のリスクが相対的に高まります。 |
・歯間ブラシやタフトブラシなど、補助的な清掃用具の活用が必須です。 ・歯科医院での定期的な専門クリーニングが特に重要になります。 |
| マウスピース矯正 | ・取り外して歯磨きができるため、衛生的です。 ・ディスバイオシスのリスクが比較的低いとされます。 |
・装置自体の洗浄を怠ると、細菌の温床になります。 ・装着時間を守るなど、ご自身の協力が治療結果を左右します。 |
歯周病のリスクを考えると、清掃しやすいマウスピース矯正は、 有力な選択肢の一つです。 しかし、どちらの装置を選んでも、日々の丁寧なセルフケアと、 歯科医院でのプロによるメンテナンスが不可欠であることに変わりはありません。
歯周外科治療や再生療法が追加で必要になるケース
歯周病が進行し、歯を支える骨が多く失われている場合、 通常の歯周基本治療だけでは、土台を十分に安定させられません。 そのようなときには、より専門的な治療が必要になります。
- 歯周外科治療(フラップ手術など) 歯ぐきを部分的に開いて、歯の根の奥深くに付着した歯石や、感染した組織を直接目で見て、徹底的に取り除く手術です。歯周病の進行を食い止め、健康な歯ぐきを取り戻すことが目的です。
- 歯周組織再生療法 歯周病で失われた骨などの組織の「再生」を促す先進的な治療法です。特殊な材料を使い、骨が再生するためのスペースを作ったり、体の再生能力を刺激する薬を使ったりします。
これらの外科的な処置は安全に矯正治療を進める上で、有益な選択肢となる場合があります。
まとめ
歯周病があるからと、きれいな歯並びを諦める必要はありません。 たしかに、歯周病を放置したまま矯正を始めると、歯が抜けたり歯ぐきが下がったりするリスクが伴います。
しかし、これらのリスクは、適切な手順を踏むことで低減させることが期待できます。 大切なのは、矯正治療の前に歯周病を徹底的に治療して健康な土台を取り戻すこと。歯と歯ぐきに無理のない、ごく弱い力で丁寧に歯を動かしていくことです。 あなたのお口の状態に合わせた治療計画を一緒に見つけることが、歯の健康を守りながら理想の歯並びを手に入れるための第一歩です。
参考文献
- Belanche Monterde A, Flores-Fraile J, Pérez Pevida E, Zubizarreta-Macho Á. “Biofilm Composition Changes During Orthodontic Clear Aligners Compared to Multibracket Appliances: A Systematic Review.” Microorganisms 13, no. 5 (2025): .
- Antonarakis GS, Zekeridou A, Kiliaridis S, Giannopoulou C. “Periodontal considerations during orthodontic intrusion and extrusion in healthy and reduced periodontium.” Periodontology 2000, no. (2024): .
- Hassan MG, Hassan DG, Hassan GA. “Tirzepatide gains US Food and Drug Administration approval for the management of obstructive sleep apnea: Implications for oral health care providers.” Journal of the American Dental Association (1939), no. (2025): .
- Alshomrani F. “Cone-Beam Computed Tomography (CBCT)-Based Diagnosis of Dental Bone Defects.” Diagnostics (Basel, Switzerland) 14, no. 13 (2024): .
- “The Hippo pathway in oral diseases and treatments: A review.” Medicine 103, no. 45 (2024): e40553.
追加情報
[title]: Biofilm Composition Changes During Orthodontic Clear Aligners Compared to Multibracket Appliances: A Systematic Review.
矯正用クリアアライナーとマルチブラケット装置におけるバイオフィルム組成変化
[quote_source]: Belanche Monterde A, Flores-Fraile J, Pérez Pevida E and Zubizarreta-Macho Á. “Biofilm Composition Changes During Orthodontic Clear Aligners Compared to Multibracket Appliances: A Systematic Review.” Microorganisms 13, no. 5 (2025): .
[title]: Periodontal considerations during orthodontic intrusion and extrusion in healthy and reduced periodontium.
健康な歯肉および歯周組織減少症における矯正治療時の歯周病に対する考慮事項
[quote_source]: Antonarakis GS, Zekeridou A, Kiliaridis S and Giannopoulou C. “Periodontal considerations during orthodontic intrusion and extrusion in healthy and reduced periodontium.” Periodontology 2000 , no. (2024): .
[title]: Tirzepatide gains US Food and Drug Administration approval for the management of obstructive sleep apnea: Implications for oral health care providers.
睡眠時無呼吸症候群(OSA)の治療薬としてのチルゼパティド
[quote_source]: Hassan MG, Hassan DG and Hassan GA. “Tirzepatide gains US Food and Drug Administration approval for the management of obstructive sleep apnea: Implications for oral health care providers.” Journal of the American Dental Association (1939) , no. (2025): .
[title]: Cone-Beam Computed Tomography (CBCT)-Based Diagnosis of Dental Bone Defects.
[quote_source]: and Alshomrani F. “Cone-Beam Computed Tomography (CBCT)-Based Diagnosis of Dental Bone Defects.” Diagnostics (Basel, Switzerland) 14, no. 13 (2024): .
[title]: The Hippo pathway in oral diseases and treatments: A review.
口腔疾患と治療におけるHippoシグナル経路
[quote_source]: and Ni D. “The Hippo pathway in oral diseases and treatments: A review.” Medicine 103, no. 45 (2024): e40553.
監修者情報
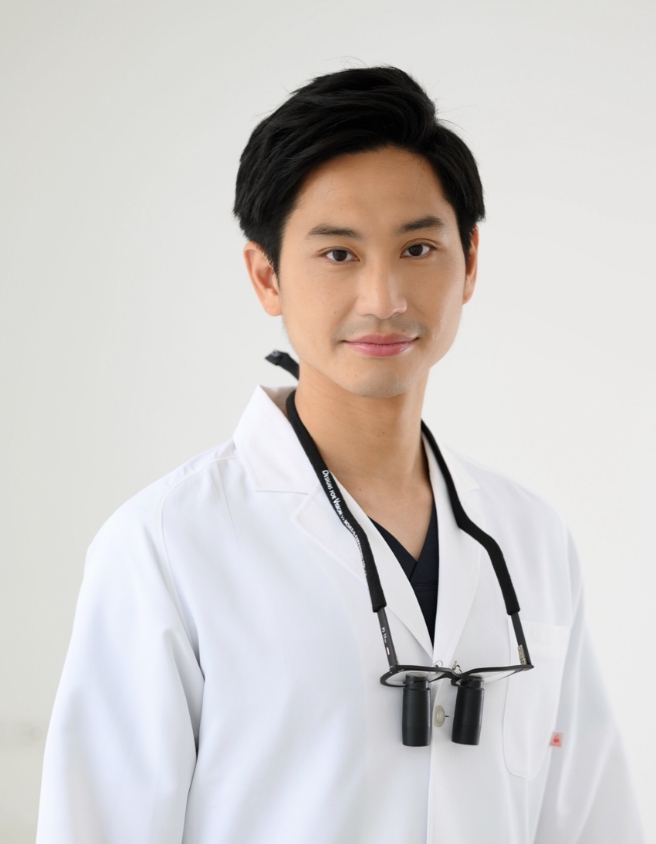
牧野歯科・矯正歯科 歯科医師
牧野 盛太郎Seitaro Makino
略歴
所属学会
- 日本口腔外科学会認定医
- 日本再生医療学会認定医
- 日本口腔外科学会
- 日本再生医療学会
- 日本顎顔面インプラント学会
- 日本口腔インプラント学会