ブログ
根管治療と抜歯はどっちがいい?メリットや注意点を歯科医師が解説
歯に激しい痛みを感じたとき、「抜いた方が楽になる?」「いや、自分の歯は1本でも多く残したい」と、多くの方が二つの選択肢の間で深く悩まれます。その決断は、あなたのこれからの食事や笑顔、そして生活の質そのものを左右する、非常に重要なものです。
実は、治療後のケアによっては歯を失うリスクが11.3倍も高まるというデータもあります。この記事では、歯を残す「根管治療」と原因を取り除く「抜歯」のどちらを選ぶべきか、メリットや費用、成功率など複数の視点から徹底比較。後悔しない選択をするために、歯科医師が判断基準を詳しく解説します。
根管治療と抜歯を比較する4つのポイント
歯に強い痛みが出たり、大きく欠けたりしたとき。 「この歯、抜かずに治せる?」「抜いた方が楽かな?」 多くの方が、このような悩みを抱えて歯科医院を訪れます。
根管治療と抜歯は、どちらも大切な治療の選択肢です。 それぞれに良い点と、知っておくべき注意点があります。 ご自身の歯の将来にとって最善の選択をするために、 4つの大切なポイントで、この2つの治療法を比べてみましょう。
治療の目的:歯を残す根管治療と原因を取り除く抜歯
根管治療と抜歯は、目指すゴールがまったく違います。 この違いを理解することが、治療法を選ぶ第一歩になります。
- 根管治療の目的
- ご自身の歯を抜かずに残すこと 重い虫歯などで細菌に感染した歯の神経を取り除き、 歯の根の中をきれいに消毒して、お薬を詰める治療です。 最大の目的は、歯そのものを抜かずに保存することです。 自分の歯を残せば、噛む感覚や見た目を維持できます。
- 抜歯の目的
- 感染や痛みの原因を根本から取り除くこと 歯を残すことが難しい場合に行われる最終的な手段です。 痛みや腫れの原因である歯を抜き取り、感染を除去します。 しかし、ご自身の歯を1本失うという大きな欠点があります。
| 治療法 | 目的 | こんなときに行われます |
|---|---|---|
| 根管治療 | 歯を抜かずに残す | ・虫歯が神経まで進んでいる ・歯の根の先に膿がたまっている |
| 抜歯 | 感染源となっている歯を取り除く | ・歯が根元まで大きく割れている ・重い歯周病で歯がグラグラ ・根管治療をしても良くならない |
メリット・デメリット:自分の歯で噛める価値と再発リスク
どちらの治療法にも、良い面と注意が必要な面があります。 ご自身の生活スタイルや価値観と合わせて考えてみましょう。
- 根管治療のメリット・デメリット
- メリット
- 自分の歯でしっかり噛む感覚を保てる
- 周りの健康な歯を削る必要がない
- 見た目の自然さを維持しやすい
- デメリット
- 治療後に再び感染するリスクがある(根尖性歯周炎)
- 神経を抜くため、歯がもろくなり割れやすくなる
- 問題が起きても痛みを感じにくく、発見が遅れる
- メリット
- 抜歯のメリット・デメリット
- メリット
- 痛みや腫れの原因を根本から除去できる
- 周りの歯や骨への悪影響を食い止められる
- デメリット
- 大切なご自身の歯を永久に失ってしまう
- 抜歯後に別の治療が必要
- 全体の噛み合わせのバランスが崩れることがある
- メリット
根管治療をしても、再び歯の根の先に病気ができることがあります。 この状態を「根尖性歯周炎」と呼びます。 その場合は、再度根管治療を行ったり、抜歯を検討したりと、 いくつかの選択肢の中から次の治療法を決める必要があります。
費用と期間の目安:保険適用の範囲と必要な通院回数
治療にかかる費用や時間は、生活に関わる重要なポイントです。
- 根管治療の場合
- 費用
- 保険適用:1本あたり数千円~1万円程度が目安です。
- 自費診療:数万円~十数万円かかることもあります。 精密な機器を使い、成功率を高めることを目指します。
- 期間
- 歯の状態によりますが、通常3~5回程度の通院が必要です。
- 根の中が複雑な場合は、数ヶ月かかることもあります。
- 費用
- 抜歯の場合
- 費用
- 基本的に保険適用で、1本あたり数千円程度です。
- 期間
- 通常は1~2回の通院で完了します。
- 費用
抜いた後、失った歯の機能を補うための治療が必須です。 ブリッジ、入れ歯、インプラントなどの費用と期間が別途かかります。 特にインプラントは自費診療となり、高額になる場合があります。
| 項目 | 根管治療 | 抜歯 |
|---|---|---|
| 費用 | 保険適用と自費診療がある | 保険適用が基本 (抜歯後の治療費は別途) |
| 期間 | 複数回の通院が必要 | 比較的短い(1〜2回) |
成功率と歯の寿命:治療後の再発可能性と将来的な展望
治療した歯が、この先どのくらい使えるのかは誰もが気になります。
- 根管治療の成功率と歯の寿命
- 根管治療の成功率は100%ではありません。 歯の根の形が複雑だと、細菌が残りやすく再発リスクは高まります。 もし再発した場合、根の先を手術する方法などもありますが、 どの治療が最適かの判断は、難しいケースもあります。
- 治療後の歯の寿命は、その後のケアで大きく変わります。 特に、ひびが入っている歯に根管治療を行った場合、 治療後に適切な被せ物をしないと、抜歯に至るリスクが 11.3倍も高くなるという研究報告があります。
- 抜歯後の展望
- 抜歯をすれば、その歯の寿命はそこで終わりになります。 しかし、ブリッジやインプラントで噛む機能は回復できます。 長期的な視点で、ご自身の生活の質を高く保てる選択を 歯科医師と一緒に考えることが大切です。
後悔しない治療選択のための5つの判断基準
「根管治療」と「抜歯」、どちらを選ぶべきか。 大切なご自身の歯だからこそ、簡単に決められないのは当然です。 しかし、それぞれの治療法を正しく理解し、ご自身の希望と 照らし合わせることで、納得のいく選択ができます。 後悔しない治療法を選ぶために、考えておきたい5つの基準を 具体的に解説します。一緒に一つずつ確認していきましょう。
あなたの歯はどっち?治療法を決める歯の状態と全身疾患
治療法を決める上で最も大切なのは、今の歯の状態です。 歯の状態によっては、選べる治療法が限られることもあります。 まずは、ご自身の歯がどのような状態か確認しましょう。
【あなたの歯の状態チェックリスト】
- 虫歯の進行度 虫歯が神経に達しているだけか、さらに進んで 歯の根の周りの骨まで溶かしていないか。
- 歯のひび(亀裂)の有無と深さ 歯に入ったひびの深さや場所によっては、歯を残すことが難しくなります。特に症状のない浅いひびであれば、すぐに治療せず経過を見るという選択肢もあります。
- 歯周病の重さ 歯を支える骨が歯周病で大きく失われていると、根管治療をしても歯がぐらぐらで残せないことがあります。
- 感染の広がり 歯の根の感染が、鼻の横にある空洞(上顎洞)まで広がり、「歯原性副鼻腔炎」を起こしている場合があります。この場合、原因を確実に取り除くために抜歯が選択されることもあります。
根管治療後の被せ物の種類:材質による見た目・費用・耐久性の違い
根管治療をした歯は、神経や血管がないためにもろくなります。 栄養が届かないため、健康な歯に比べて割れやすい状態です。 そのため、歯を守るために「被せ物(クラウン)」が不可欠です。
被せ物には様々な種類があり、それぞれに特徴があります。
| 材質の種類 | 見た目(審美性) | 耐久性 | 費用(保険適用) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 銀歯(金属) | △(銀色で目立つ) | ◎(非常に硬い) | 〇(比較的安い) | 奥歯など、強度を優先したい場所に使われます。 |
| CAD/CAM冠 | 〇(白い) | △(割れやすい) | 〇(条件あり) | 白いですが、年数が経つと変色することがあります。 |
| セラミック | ◎(天然の歯に近い) | 〇(割れることがある) | ×(自費診療) | 見た目がとても自然で、汚れもつきにくい材質です。 |
| ジルコニア | ◎(白い) | ◎(非常に硬い) | ×(自費診療) | 強度と美しさを兼ね備えた、セラミックの一種です。 |
抜歯後の3つの選択肢:ブリッジ・入れ歯・インプラントの比較
残念ながら抜歯となった場合でも、失った歯の機能を補うための方法がいくつかあります。 根管治療をしても治らない歯の治療選択肢の一つが抜歯であり、 その後の処置が、お口全体の健康を左右します。 歯がない状態を放置すると、様々な問題につながります。 隣の歯が倒れてきたり、全体の噛み合わせが悪くなったりします。
| 治療法 | メリット | デメリット | 費用 | 治療期間 |
|---|---|---|---|---|
| ブリッジ | ・固定式で違和感が少ない ・保険適用が可能 |
・健康な両隣の歯を削る ・支えの歯に負担がかかる |
保険/自費 | 短い |
| 入れ歯 | ・両隣の歯をほぼ削らない ・保険適用で安価 |
・違和感や異物感がある ・硬いものが噛みにくい |
保険/自費 | 短い |
| インプラント | ・自分の歯のように噛める ・周りの歯に負担がない |
・外科手術が必要 ・治療期間が長い ・自費診療で高額 |
自費 | 長い |
治療の痛みは?麻酔や痛みを最小限に抑える歯科医院の取り組み
「歯の治療は痛い」というイメージから、不安は大きいでしょう。 しかし、現在の歯科治療では、痛みを最小限にする工夫があります。 痛みをできるだけ感じないように、様々な取り組みが行われています。
【痛みを抑えるための取り組み例】
- 表面麻酔 麻酔注射の針を刺す歯ぐきの表面にジェルなどを塗り、チクッとする痛みを和らげます。
- 極細の注射針 針が細いほど、刺す時の痛みは少なくなります。
- 十分な麻酔時間 麻酔がしっかり効くまで時間を置いてから治療を始め、治療中の痛みを防ぎます。
信頼できる歯科医院の探し方とセカンドオピニオンの重要性
根管治療も抜歯も、歯科医師の技術や経験が結果を左右します。 そのため、信頼できる歯科医師・歯科医院を選ぶことが重要です。
【歯科医院を選ぶ際のチェックポイント】
- 十分な説明をしてくれるか 歯の現状、治療の選択肢、それぞれの長所・短所、費用や期間について、納得できるまで説明してくれるか。
- 精密な診断・治療ができる設備があるか CT(三次元レントゲン)やマイクロスコープ(歯科用顕微鏡)は、より正確な診断と、安全で精密な治療につながります。
- 衛生管理が徹底されているか 治療器具の滅菌など、感染対策がきちんと行われているか。
また、治療法の選択に迷った時は、「セカンドオピニオン」を 聞くことをお勧めします。 根管治療後の状態が良くない場合の治療法など、 専門家の間でも意見が分かれることがあります。 別の歯科医師の意見を聞くことで、より広い視点から検討でき、 ご自身が安心して治療の決断を下せるようになります。
まとめ
今回は、根管治療と抜歯について、様々な角度から比較し、後悔しないための判断基準をご紹介しました。 どちらの治療法にも一長一短があり、どちらが絶対的に良いという答えはありません。
最も大切なのは、精密な検査でご自身の歯の状態を正しく把握し、「将来どのようなお口で過ごしたいか」を歯科医師としっかり共有することです。 自分の歯で噛める喜びを優先するのか、それとも原因を確実に取り除き、再発のリスクを減らすことを選ぶのか。 費用や期間、見た目の希望なども含め、あなたの価値観をぜひお聞かせください。
一人で悩まず、まずは信頼できる歯科医師に相談することが、最善の選択への第一歩です。 もし迷いがあれば、セカンドオピニオンも活用しながら、あなたが心から納得できる治療法を一緒に見つけていきましょう。
参考文献
- Corbella S, Walter C, Tsesis I. “Effectiveness of root resection techniques compared with root canal retreatment or apical surgery for the treatment of apical periodontitis and tooth survival: A systematic review.” International endodontic journal 56 Suppl 3, no. (2023): 487-498.
- Maldupa I, Innes N, Viduskalne I, Brinkmane A, Senakola E, Krumina K, Uribe SE. “Clinical effectiveness/child-patient and parent satisfaction of two topical fluoride treatments for caries: a randomised clinical trial.” Scientific reports 14, no. 1 (2024): 8123.
- and Blum JS. “Management Options and Outcomes for Root-Filled Teeth That Have a Periapical Radiolucency.” Australian endodontic journal : the journal of the Australian Society of Endodontology Inc 51, no. 1 (2025): 10-16.
- Pannkuk TF, Craig JR, Tušas P, Simuntis R. “Management of Endodontic Disease for Odontogenic Sinusitis.” Otolaryngologic clinics of North America 57, no. 6 (2024): 1119-1138.
- Zhang S, Xu Y, Ma Y, Zhao W, Jin X, Fu B. “The treatment outcomes of cracked teeth: A systematic review and meta-analysis.” Journal of dentistry 142, no. (2024): 104843.
追加情報
[title]:
根管再治療や頂点手術と比較した根切り術の有効性と歯の生存率:システマティックレビュー 【要約】
- 背景:根管充填された上顎および下顎の大臼歯における頂点歯周炎の管理には、歯を失わないために根切り術が用いられる場合がある。
- 目的:本研究の目的は、非外科的な根管再治療や頂点手術と比較して、根切り術(根切り/冠切り/根切断)の頂点歯周炎管理における効果を臨床的および患者関連のアウトカム(PROMS)の評価によって系統的に分析することである。
- 方法:2021年9月25日までPubMed、MEDLINE(OVIDインターフェース経由)、EMBASE、Cochrane Centralで電子文献検索を行い、グレーリテラチャーの手動検索を補完した。頂点歯周炎の治療における根切り術のアウトカム(歯の生存率および患者報告されたアウトカムメジャー)を報告した無作為化比較試験、比較臨床試験、観察研究が同定された。バイアスのリスクはニューカッスル・オタワスケールを用いて評価された。
- 結果:総報告数2098件のうち、36件がさらなるスクリーニングの対象となった。2018年から2020年に発表された3つの後ろ向き研究がこのシステマティックレビューに含まれている。プロトコル、研究デザイン、報告されたアウトカムにおいて高い異質性が観察された。バイアスのリスクは低から中程度であった。これらの3つの研究は、1〜16.8年の追跡期間内に254名の患者から得られた305本の切除歯のデータを含んでいた。全体として、追跡期間中に151本の歯が抜歯された。これらの研究では、根切り治療は42本の歯に対して根管治療目的で行われた。これらの研究のうち1つは、追跡時に23本中12本の歯の喪失を報告していた。どの研究もPROMSについて報告していなかった。
- 議論・結論:頂点歯周炎を治療するために根切り術が使用されることはあるが、データは限られている。さらに、研究は非常に異質であり、バイアスのリスクが高いとされている。
- 結論:現在の利用可能なエビデンスのレベルでは、頂点歯周炎の管理において根切り術を推奨することも否定することもできない。
- 登録:PROSPEROデータベース (CRD42021260306)。 以上、要約しました。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35920073
[quote_source]: Corbella S, Walter C and Tsesis I. “Effectiveness of root resection techniques compared with root canal retreatment or apical surgery for the treatment of apical periodontitis and tooth survival: A systematic review.” International endodontic journal 56 Suppl 3, no. (2023): 487-498.
[title]: Clinical effectiveness/child-patient and parent satisfaction of two topical fluoride treatments for caries: a randomised clinical trial.
乳児歯のむし歯予防における2種類のフッ素治療の臨床的有効性と患者と保護者の満足度:無作為化臨床試験 【要約】
- 乳児のむし歯治療における最適な銀ダイミンフルオライド(SDF)の使用法や新しい製品の有効性に関する知識の欠如があります。
- 本研究では、6つの治療プロトコル(P1/P2/TF1/TF2/SDF1/SDF2)を含む、BM(行動修正)と組み合わせた3つの化合物(P/SDF/TF)の効果を評価しました。
- 大きな合併症(根管治療/抜歯/疼痛)を予防する効果を評価しました。
- 研究はラトビアの大学クリニックで1/9/2020から31/8/2022まで行われ、373人の乳児(87.3%)が研究を完了しました。
- SDF2は、大きな合併症(21.5%、OR=0.28)および小さな合併症(OR=0.16)の発生率およびリスクが有意に低く、全体の満足度は96%でした。
- SDFを2回/年の使用法とBMとの組み合わせは、乳幼児のむし歯の大きな合併症を効果的に予防し、子供と保護者によく受け入れられました。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38582806
[quote_source]: Maldupa I, Innes N, Viduskalne I, Brinkmane A, Senakola E, Krumina K and Uribe SE. “Clinical effectiveness/child-patient and parent satisfaction of two topical fluoride treatments for caries: a randomised clinical trial.” Scientific reports 14, no. 1 (2024): 8123.
[title]: Management Options and Outcomes for Root-Filled Teeth That Have a Periapical Radiolucency.
根管充填済み歯の歯根周囲病変に対する治療選択肢と予後 【要約】
- 根管治療後の歯根周囲病変(PTED:Post-treatment endodontic disease)は、根管治療済みの歯に治癒傾向のない歯根周囲の透過像(病変)が存在する場合に診断されます。
- PTEDの治療選択肢は、基本的に3つに限定されます。①経過観察(再評価)、②根管再治療(外科的または非外科的)、③抜歯(根尖切除を含む)。
- 本論文では、PTEDの治療選択肢に関する最新の臨床的に関連性の高い情報を提供することを目的としています。病因、症例選択、予後といった観点から、臨床医が患者への治療法を選択する際に役立つ情報を提示しています。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40151135
[quote_source]: and Blum JS. “Management Options and Outcomes for Root-Filled Teeth That Have a Periapical Radiolucency.” Australian endodontic journal : the journal of the Australian Society of Endodontology Inc 51, no. 1 (2025): 10-16.
[title]: Management of Endodontic Disease for Odontogenic Sinusitis.
歯原性副鼻腔炎に対する根管治療の管理 【要約】
- 歯原性副鼻腔炎(ODS)は、歯髄壊死や根尖性歯周炎などを伴う歯内感染が原因で発生する。
- ODSの一次的な歯科治療としては、抜歯と根管治療(RCT)がある。
- RCTが膿性ODSの治療に有効であるという証拠は乏しく、多くのRCT関連の報告は、反応性の上顎洞粘膜炎の解決における成功率について言及しているに過ぎない。
- 抜歯はODSの原因となる歯内疾患に対する最も確実な治療法であるが、機能的な歯を失うという欠点があり、それでも膿性副鼻腔炎が解決しないことが多い。
- 本論文では、RCTと抜歯の手技の重要な概念、およびODS解決におけるそれぞれの成功率について報告された知見を強調している。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39214736
[quote_source]: Pannkuk TF, Craig JR, Tušas P and Simuntis R. “Management of Endodontic Disease for Odontogenic Sinusitis.” Otolaryngologic clinics of North America 57, no. 6 (2024): 1119-1138.
[title]: The treatment outcomes of cracked teeth: A systematic review and meta-analysis.
亀裂した歯の治療成績:系統的レビューおよびメタ分析 【要約】
- このレビューの目的は、歯のパルプを保持する亀裂した歯 (CT-VDP) または根管治療を行う亀裂した歯 (CT-RCT) の臨床的な治療成績を分析することである。
- 研究選択のために、Medline、Embase、PubMed、Cochrane Library のデータベースで系統的な検索が行われた。
- 1年以上の追跡期間を持つ歯生存率 (TSR)、パルプ生存率 (PSR)、成功率 (SR) を評価する研究が含まれた。
- 27の研究が定性的な分析を受け、そのうち26はメタ分析に含まれた。修復処置を行わない監視のSRは、3年で80%であった。
- CT-VDPのTSRは、1〜6年で92.8〜97.8%、CT-VDPのPSRは、1〜3年で85.6〜90.4%、CT-VDPのSRは、1〜3年で80.6〜89.9%であった。
- CT-RCTのTSRは、1〜2年で90.5〜91.1%、CT-RCTのSRは、1〜4年で83.0〜91.2%であった。
- CT-VDPのカスプカバーのない直接修復は、パルプ合併症のリスク比 (RR = 3.2, 95% CI: 1.51-6.82, p = 0.002) および歯抜歯のリスク比 (RR = 8.1, 95% CI: 1.05-62.5, p = 0.045) をフルクラウン修復と比較して増加させた。
- フルクラウン修復を行わないCT-RCTは、フルクラウン修復を行うCT-RCTと比較して、歯抜歯のリスクが11.3倍高かった (p < 0.001)。
- 無症状のCTには修復処置を行わない監視が選択肢となり得る。CT-VDPのカスプカバーのない直接修復は、フルクラウン修復と比較してパルプ合併症と歯抜歯のリスクを有意に増加させる。CT-RCTにはフルクラウン修復が強く推奨される。
- 無症状のCTには修復処置を行わない監視が選択肢となり得る。CTに症状がある場合やCT-RCTにはフルクラウン修復が強く推奨される。 【参考】
- 著作権情報: 2024年 Elsevier Ltd. 全著作権所有 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38272437
[quote_source]: Zhang S, Xu Y, Ma Y, Zhao W, Jin X and Fu B. “The treatment outcomes of cracked teeth: A systematic review and meta-analysis.” Journal of dentistry 142, no. (2024): 104843.
監修者情報
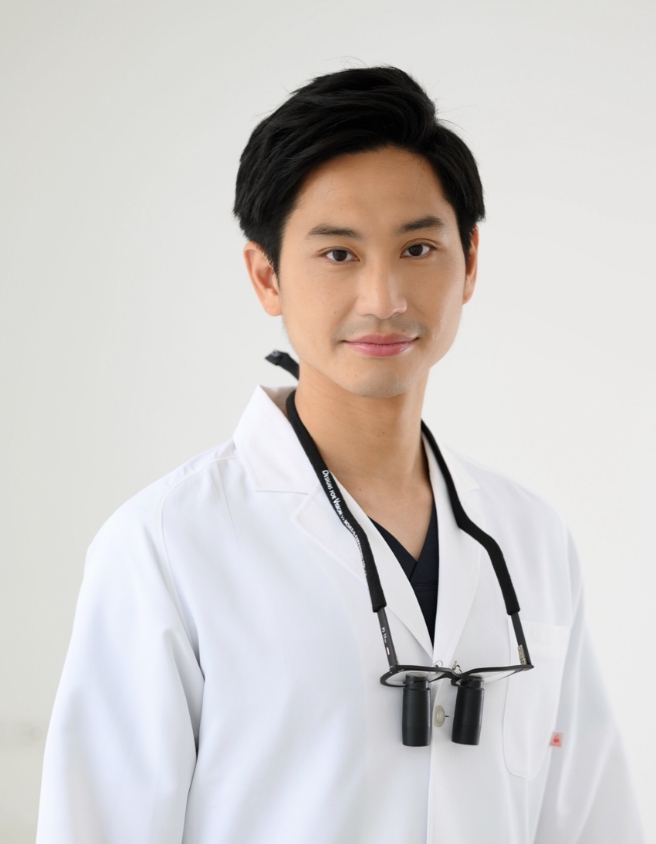
牧野歯科・矯正歯科 歯科医師
牧野 盛太郎Seitaro Makino
略歴
所属学会
- 日本口腔外科学会認定医
- 日本再生医療学会認定医
- 日本口腔外科学会
- 日本再生医療学会
- 日本顎顔面インプラント学会
- 日本口腔インプラント学会