ブログ
最近朝晩が寒くなってきてから、冷たいものを飲んだり、歯ブラシを当てると歯がしみるようになった。
秋から冬へ、季節が移り変わる時期は朝晩の冷え込みが強まります。 「冷たい水でうがいをすると、歯がキーンとしみる」 「歯磨きの時に、ピリッとした痛みが走るようになった」 このようなお悩みで、クリニックを受診される患者さんが増えてきます。
急な気温の変化で歯が痛むのは、決して気のせいではありません。 寒暖差は、お口の中の健康にも、実は大きな影響を与えているのです。 その痛みの原因は、もしかしたら「知覚過敏」かもしれません。
この記事では、なぜ寒暖差で歯が痛むのか、その原因を掘り下げます。 ご自身で症状を確認できる、簡単なチェック方法も解説します。 歯の痛みに悩むあなたの不安が、少しでも軽くなるようお手伝いします。
象牙質が露出するメカニズムと「キーン」と痛む理由
歯が「キーン」と痛む仕組みを知るために、歯の構造を見てみましょう。 私たちの歯は、硬いよろいを着た、とても繊細な組織でできています。
- エナメル質 歯の一番外側を覆う、人間の体で最も硬い部分です。 水晶と同じくらいの硬さで、歯の内部を刺激から守っています。 この部分には神経がないため、削っても痛みを感じることはありません。
- 象牙質(ぞうげしつ) エナメル質の内側にある、少し黄色みがかった部分です。 象牙質には「象牙細管(ぞうげさいかん)」という、無数の細い管が通っています。 この管は、歯の中心部にある神経(歯髄)までつながるトンネルのようなものです。
- 歯髄(しずい) 歯の神経や血管が集まっている、歯の「心臓部」です。 歯に栄養を届けたり、痛みなどの感覚を脳に伝えたりします。
通常、象牙質は硬いエナメル質によってしっかりと守られています。 そのため、冷たいものなどを口にしても、痛みを感じることはありません。 しかし、何らかの原因でエナメル質が傷ついたり、歯ぐきが下がったりすると、象牙質がむき出しになってしまいます。
この状態になると、象牙細管というトンネルを通じて、外部からの刺激が歯の神経(歯髄)に直接伝わってしまいます。 これが、冷たいものや歯ブラシが触れた時に「キーン」と感じる、鋭い痛みの正体です。
これは虫歯?知覚過敏と虫歯・歯周病の痛みの違い
歯がしみるように痛むと、「虫歯かもしれない」と心配になりますよね。 知覚過敏と虫歯、そして歯周病は、痛みの性質にそれぞれ特徴があります。 ご自身の症状と下の表を見比べて、痛みの原因を探る参考にしてください。
ただし、これはあくまで目安であり、自己判断は禁物です。 正確な診断のためには、必ず歯科医院を受診するようにしましょう。
| 症状の種類 | 痛みの特徴 | 痛みが起こるタイミング |
| 知覚過敏 | ・一瞬で消える鋭い痛み ・「キーン」「ピリッ」と響く感じ |
・冷たいものや熱いものを口にした時 ・歯ブラシが触れた時 ・甘いもの、酸っぱいものを食べた時 ・冷たい空気を吸い込んだ時 |
| 虫歯 | ・持続的な痛み ・「ズキズキ」と脈打つような痛み |
・何もしなくても痛むことがある ・温かいもので痛みが強くなることがある ・食べ物が歯の穴につまると痛む |
| 歯周病 | ・歯ぐきが腫れたような鈍い痛み ・歯が浮いたような、押されるような感じ |
・歯磨きの時に歯ぐきから出血する ・硬いものが噛みにくい ・歯ぐきを押すと痛みや膿が出ることがある |
知覚過敏だと思っていたら、実は虫歯が神経の近くまで進行していた、というケースは決して珍しくありません。 痛みの種類である程度の見当はつきますが、複数の原因が重なっている可能性も十分に考えられます。
歯ぎしりや食いしばり、酸蝕症も痛みを引き起こす
知覚過敏の原因は、歯ぐきが下がることだけではありません。 毎日の生活の中にある、自分では気づきにくい癖や食習慣が、歯に大きなダメージを与えている可能性があります。
歯ぎしり・食いしばり
睡眠中や、何かに集中している時に、無意識に歯を強く噛みしめていませんか。 こうした癖は、ご自身が思っている以上に強い力で歯に負担をかけます。
- 歯の表面のエナメル質が、ヤスリで削るようにすり減ってしまいます。
- 歯の根元に力が集中し、エナメル質にひびが入ったり、欠けたりします。
- 歯だけでなく歯ぐきにも負担がかかり、歯ぐきが下がる原因になります。
酸蝕症(さんしょくしょう)
酸蝕症とは、食べ物や飲み物に含まれる「酸」によって、歯のエナメル質が溶かされてしまう状態を指します。 虫歯は細菌が原因ですが、酸蝕症は化学的に歯が溶けるのが特徴です。
- 原因となりやすい飲食物の例 炭酸飲料、スポーツドリンク、柑橘系の果物やジュース、お酢やドレッシング、ワインなど
- 特徴 虫歯菌が原因ではないため、歯磨きをしっかりしていても起こる可能性があります。 特に、時間をかけて少しずつ飲む「だらだら飲み」は、お口の中が酸性の状態が続くため、リスクが高まります。
このように、日々の生活習慣が知覚過敏の引き金になることは少なくありません。 原因を正しく特定し、適切に対処することが、症状の改善と再発防止につながります。
5項目で確認!自宅でできる知覚過敏チェックリスト
ご自身の歯のしみる症状が、知覚過敏によるものか、簡単なリストで確認してみましょう。 以下の項目に、当てはまるものがあるかチェックしてみてください。
【知覚過敏セルフチェック】
1. 冷たい水やアイスクリームを食べると、歯が「キーン」としみる。
2. 歯磨きの時、歯ブラシの毛先が特定の歯に当たると「ピリッ」と痛む。
3. 甘いチョコレートやケーキを食べた時に、しみるような痛みを感じる。
4. レモンやオレンジなど、酸っぱいものを食べると歯が痛む。
5. 冬の寒い日に、冷たい空気を吸い込むと歯がしみる感じがする。
【チェック結果の目安】
- 1〜2つ当てはまる方 知覚過敏の初期段階の可能性があります。 これ以上悪化させないよう、歯に優しい歯磨きを心がけましょう。
- 3つ以上当てはまる方 知覚過敏が進行している可能性が考えられます。 痛みが続く場合は、一度歯科医院で相談することをおすすめします。
このチェックリストは、あくまでご自身の状態を知るための目安です。 一つでも当てはまる項目があり、日常生活で不便を感じている場合は、決して我慢しないでください。 痛みの裏には、虫歯などの他の病気が隠れている可能性もありますので、早めに歯科医師に相談しましょう。
歯科医院で行う知覚過敏の主な治療法4選
ご自宅でのセルフケアを頑張っても、歯の「キーン」とする痛みが続くと、とても不安になりますよね。 歯科医院では、知覚過敏の症状や原因を詳しく調べ、あなたに合った治療法をご提案することができます。
治療には、歯を削らずにお薬を塗るだけの簡単な処置もあります。 また、しみる原因となっている部分をしっかり保護する方法もあります。 これからご紹介する4つの治療法を知ることで、歯科医院での治療に対する不安が少しでも和らげば幸いです。
薬剤塗布で刺激をブロックする薬物塗布療法
薬物塗布療法は、知覚過敏の治療で最初に行われることが多い、歯に負担の少ない治療法です。 しみる原因となっている歯の表面に、専用の薬剤を直接塗ることで、痛みを和らげることを目指します。
どのような仕組みで痛みを抑えるの?
歯がしみるのは、歯の内部にある「象牙質(ぞうげしつ)」がむき出しになっているためです。 象牙質には、「象牙細管(ぞうげさいかん)」という無数の細い管が通っています。 この管が、冷たいものなどの刺激を歯の神経に伝えてしまうのです。
この治療では、象牙細管の入り口を塞ぐ成分が入ったお薬を塗ります。 トンネルの入り口にフタをするようなイメージです。 これにより、外部からの刺激が神経に届きにくくなり、しみる症状が抑えられます。
薬物塗布療法の主なメリット
- 歯を削る必要がない 歯の表面にお薬を塗るだけなので、歯そのものへのダメージがありません。
- 治療中の痛みがほとんどない 麻酔なども不要で、痛みを感じることはほとんどありません。
- 治療時間が短い 1回の治療は、数分程度で終わることがほとんどです。
この治療は、特に症状が比較的軽い場合に効果を発揮しやすいです。 ただし、効果が続く時間には個人差があり、症状が戻るようであれば、何度か繰り返し塗布することがあります。 まずは負担の少ない治療から試してみたい、という方に適した方法です。
露出した象牙細管を塞ぐレジン充填(詰め物)治療
お薬を塗るだけでは症状がなかなか改善しない場合に選択される治療法です。 また、歯のすり減りなどで象牙質が大きく露出している場合にも行われます。 歯科用のプラスチック(レジン)で、しみる部分を直接覆って保護します。
どのような場合に行う治療?
この治療は、特に以下のようなケースで効果的です。
- 歯の根元がえぐれるように削れている(くさび状欠損)
- 歯ぎしりや食いしばりで、歯の噛み合わせの面がすり減っている
- 歯が少し欠けたり、ヒビが入ったりして、象牙質が見えている
レジン充填治療のメリットと特徴
- 物理的に刺激を遮断できる 露出した象牙質を直接コーティングするため、薬剤塗布に比べて、効果が長持ちしやすい傾向があります。
- 見た目が自然に仕上がる 歯の色に近い材料を使うため、治療した箇所が目立ちにくいです。
- 1〜2回の通院で完了する 多くの場合、少ない通院回数で治療を終えることができます。
歯の状態によっては、詰め物がはがれないように接着力を高めるため、表面を少しだけ整えることがあります。 しみる原因となっている部分を物理的にカバーすることで、冷たいものや歯ブラシの刺激から歯をしっかりと守ることができます。
保険適用はどこまで?治療法ごとの費用と期間の目安
治療を受けるにあたり、費用や通院回数がどれくらいかかるのかは、とても気になる点だと思います。 知覚過敏の治療の多くは健康保険が適用されますが、治療法によっては自費診療となる場合もあります。 それぞれの治療法にかかる費用と期間の目安を、下の表にまとめました。
| 治療法 | 保険適用 | 費用目安(3割負担の場合) | 期間・回数の目安 |
| 薬物塗布療法 | 適用 | 1歯あたり数百円〜1,000円程度 | 1回〜数回(症状による) |
| レジン充填治療 | 適用 | 1歯あたり1,500円〜3,000円程度 | 1回〜2回 |
治療費について知っておきたいポイント
- 上記の金額は、治療そのものにかかる費用の目安です。 初診料や再診料、レントゲンなどの検査料が別途必要になります。
- 治療する歯の本数や症状の重さ、歯科医院の方針によって費用は変わります。
これらの治療法で改善が見られないほど重度の知覚過敏の場合は、最終的な手段として、歯の神経を取り除く治療(根管治療)が必要になることもあります。
治療を始める前には、必ず担当の歯科医師から治療内容、費用、期間について詳しい説明があります。 わからないことや不安なことがあれば、決して遠慮せず質問して、ご自身が納得した上で治療に進むようにしましょう。
今日から始める知覚過敏の再発を防ぐ5つの習慣
歯の「キーン」とするつらい痛みは、歯科医院の治療で一時的に良くなります。 しかし、痛みの原因が毎日の生活習慣にある場合、再発してしまうことがあります。 「またあの痛みが戻ってきたらどうしよう」と不安に思う方もいるかもしれません。
でも、ご安心ください。 知覚過敏は、毎日のちょっとした心がけで、再び起こるリスクを大きく減らせます。 これからご紹介する5つの習慣を今日から始めて、快適な毎日を取り戻しましょう。 痛みを気にせず、食事や会話を楽しめるようになるためのお手伝いをします。
硝酸カリウム配合など歯磨き粉の選び方と正しい使い方
知覚過敏の症状を和らげるためには、歯磨き粉選びがとても大切です。 毎日使うものだからこそ、ご自身の症状に合った製品を選びましょう。 薬局などでは多くの種類が売られていますが、成分表示に注目してみてください。
【知覚過敏に効果が期待できる主な成分】
| 成分の種類 | 働きの仕組み |
| 硝酸カリウム | 歯の神経の周りにイオンのバリアを作ります。 刺激が神経に伝わるのを防ぐ、信号のブロック役です。 |
| 乳酸アルミニウム | 刺激が伝わるトンネル(象牙細管)の入り口を直接ふさぎます。 刺激そのものが中に入らないようにフタをします。 |
これらの成分が含まれる「知覚過敏用」と書かれた歯磨き粉がおすすめです。 また、歯を強くして虫歯を防ぐ「フッ素」が配合されているものを選びましょう。 研磨剤(清掃剤)が少ない、あるいは無配合の製品は、歯の表面を傷つけにくいため、より優しく磨くことができます。
【歯磨き粉の正しい使い方】
- 適量を歯ブラシにのせる 歯ブラシの毛の長さの半分から3分の2程度が目安です。 つけすぎると泡立ちすぎてしまい、短時間で磨いた気になってしまう原因になります。
- 歯全体に広げる 磨き始める前に、歯磨き粉を歯の表面全体に優しく塗り広げましょう。 薬用成分を、しみる部分を含めたすべての歯に行き渡らせるためです。
- やさしく丁寧に磨く 力を入れすぎず、1本1本を丁寧に磨くことを意識してください。 詳しい磨き方は、次の項目で解説します。
- すすぎはごく軽く 歯磨きの後、薬用成分を歯に長く留めることがとても重要です。 大さじ1杯(約15ml)ほどの少量の水で、5秒ほど軽くすすぐだけにしましょう。 何度もうがいをすると、せっかくの成分が流れてしまい効果が薄れてしまいます。
歯ブラシの圧は150gが目安!歯茎を傷つけない磨き方
「汚れをしっかり落としたい」という気持ちから、つい力を入れて磨いていませんか。 実は、強すぎるブラッシングは、歯と歯ぐきを傷つける大きな原因になります。 歯の表面のエナメル質を削ったり、歯ぐきを後退させたりしてしまうのです。 その結果、刺激に敏感な象牙質が露出し、知覚過敏を悪化させてしまいます。
歯磨きの理想的な圧は、150g〜200gと言われています。 これは、歯ブラシの毛先がフワッと歯に触れるくらいの、とても優しい力です。 一度、ご自宅のキッチンスケールに歯ブラシを押し当ててみてください。 150gがどれほど軽い力なのか、体感してみることをおすすめします。
【歯と歯ぐきを傷つけない磨き方のポイント】
- 持ち方を変える 鉛筆を持つように軽く握る「ペングリップ」がおすすめです。 グーで握る「パームグリップ」よりも、余計な力が入りにくくなります。
- 歯ブラシを小刻みに動かす 5mm〜10mmくらいの小さな幅で、歯を1〜2本ずつ丁寧に磨きましょう。 大きくゴシゴシ動かすと、歯の隙間や歯と歯ぐきの境目に毛先が届きません。
- 歯ブラシを選ぶ 毛のかたさは「ふつう」か「やわらかめ」を選びましょう。 ヘッドが小さい歯ブラシは、お口の隅々や奥歯まで届きやすいです。
毎日の歯磨きは、歯を「磨く」というより「いたわる」ような気持ちで行うことが、知覚過敏の再発予防につながります。
酸っぱい飲食物に注意!歯を守る食生活のポイント
健康や美容によいとされるお酢ドリンク、リフレッシュのための炭酸飲料。 これらに含まれる「酸」が、知覚過過敏の原因になることがあります。 酸は、歯の表面を覆う硬いエナメル質を、化学的に溶かしてしまう性質があります。 この状態を「酸蝕症(さんしょくしょう)」と呼びます。
酸蝕症は、虫歯菌が原因ではないため、歯磨きをしっかりしていても起こります。 エナメル質が薄くなることで内側の象牙質が露出し、歯がしみやすくなるのです。
【注意したい酸性の飲食物の例】
- 飲み物 炭酸飲料、スポーツドリンク、栄養ドリンク、柑橘系ジュース、お酢ドリンク、ワインなど
- 食べ物 レモンやグレープフルーツなどの柑橘類、酢の物、ドレッシングなど
【酸から歯を守るための食生活の工夫】
- だらだらと食べたり飲んだりしない お口の中が酸性の状態にある時間が長いほど、歯は溶けやすくなります。 時間を決めて飲食し、お口の中が中性に戻る時間を作りましょう。
- 酸っぱいものを口にしたら水でうがいをする お口の中の酸を洗い流し、中性に近づける手助けになります。
- 食後すぐの歯磨きは避ける 酸に触れた歯の表面は、一時的に柔らかく傷つきやすい状態です。 食後30分ほど時間をおいてから磨くことで、歯を守ることができます。
- ストローを使う 酸性の飲み物を飲む時は、ストローを使いましょう。 飲み物が前歯に直接触れるのを防ぐ、とても有効な方法です。
無意識の癖にアプローチする歯ぎしり・食いしばり対策
寝ている間や、日中に何かに集中している時、無意識に歯を食いしばっていませんか。 「歯ぎしり」や「食いしばり」は、ご自身の体重以上の非常に強い力で歯に負担をかけます。 その力は、歯の表面をすり減らし、目に見えない細かいひびを入れる原因になります。 これが、知覚過敏を引き起こす大きな要因の一つです。
まずは、ご自身に歯ぎしりや食いしばりの癖がないか、確認してみましょう。
【歯ぎしり・食いしばり セルフチェック】
- 朝起きた時に、あごの筋肉に疲れや痛みを感じる。
- 歯の先端がすり減って、平らになっているように感じる。
- 頬の内側の粘膜に、噛んだ跡のような白い線がある。
- 家族から、寝ている時の歯ぎしりを指摘されたことがある。
これらの項目に当てはまる場合は、対策が必要です。 日中は、意識的に上下の歯が触れないように気をつけましょう。 本来、リラックスしている時、唇を閉じていても上下の歯は少し離れています。 「歯を離す」「力を抜く」と書いたメモを、目につく場所に貼っておくのも効果的です。
最もダメージが大きい就寝中の歯ぎしりには、歯科医院で作る「ナイトガード」というマウスピースが有効です。 あなたの歯型に合わせて作るため、市販のものよりもしっかりとフィットします。 歯ぎしりの強い力から歯を保護する役割が期待できます。
歯科医院での定期検診とプロによるクリーニングの重要性
知覚過敏の症状が改善しても、それがゴールではありません。 再発を防ぎ、お口全体の健康を長く維持するためには、歯科医院での定期的なチェックが不可欠です。 毎日のセルフケアだけでは、どうしても磨き残しは出てしまいます。 そこから虫歯や歯周病が進行し、歯ぐきが下がることで、知覚過敏が再発する原因にもなります。
【定期検診の3つの大きなメリット】
- 1. 病気の早期発見・早期治療 知覚過敏の再発だけでなく、自分では気づきにくい初期の虫歯や歯周病を、痛みが出る前に発見できます。 早い段階で対処できれば、治療の負担も少なく済みます。
- 2. プロによる専門的なクリーニング(PMTC) 毎日の歯磨きでは落としきれない歯石や、細菌の塊である「バイオフィルム」を徹底的に除去します。 歯の表面がツルツルになることで、汚れそのものが付きにくくなる予防効果があります。
- 3. セルフケアの質の向上 歯科医師や歯科衛生士が、あなたの磨き方の癖や歯並びに合った、より適切なブラッシング方法を指導します。 ご自宅でのケアの質を高めることが、再発防止の確実な一歩です。
特に症状がなくても、3ヶ月から半年に一度は歯科医院を受診しましょう。 お口の状態をチェックしてもらう習慣が、将来のあなたの歯を守るためにとても重要です。
[title]: Efficacy of different interventions on the morbidity of the palatal donor area after free gingival graft and connective tissue graft: A systematic review.
遊離歯肉移植および結合組織移植後の口蓋供与部における罹患率に対する様々な介入の有効性:系統的レビュー 【要約】
- 本レビューは、遊離歯肉移植および結合組織移植術後の術後疼痛治療における口蓋供与部に用いられる様々な介入の有効性、および口腔健康関連QOL(OHRQOL)への影響を評価することを目的とした。
- PRISMAに基づき、4つの電子データベースとグレイ文献を検索した。
- 発見された介入は、生物学的妥当性と作用機序に基づいて分類された:機械的バリア、局所薬、止血剤、その他の療法(光線力学療法、オゾン療法など)。
- 54件の研究が選択され、43種類の異なる介入が報告された。
- 最も一般的に報告された介入は、単独または他の介入と組み合わせて使用されたコラーゲン止血スポンジであり、次いで血小板濃厚フィブリンと光線力学療法が続いた。
- 視覚的アナログ尺度(VAS)を用いた術後疼痛評価は、一般的に介入によって時間の経過とともに疼痛が改善することを示した。
- しかし、多くの研究が異なる作用機序を持つ異なる介入を組み合わせているため、介入の優位性を比較することは困難である。
- OHRQOLも時間の経過とともに改善を示したが、検証済みのツールを使用した研究が少なかったため、介入間の比較は限られている。
- 研究間の方法論的多様性は著しく、個々の研究の解釈には注意が必要である。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40151832
[quote_source]: Leite GG, Viana KSS, Cota LOM, Abreu LG, Esteves Lima RP and Costa FO. “Efficacy of different interventions on the morbidity of the palatal donor area after free gingival graft and connective tissue graft: A systematic review.” The Japanese dental science review 61, no. (2025): 31-40.
[title]: Effect of habitual cold exposure on brown adipose tissue activity in Arctic adults: a systematic review.
北極圏成人にみられる習慣的な寒冷暴露が褐色脂肪組織活性に及ぼす影響:系統的レビュー 【要約】
- 褐色脂肪組織(BAT)は、非ふるえ性熱産生において重要であり、北極圏環境における人間にとって重要な適応機構である。
- 成人におけるBATの存在発見は、肥満、II型糖尿病、心血管疾患への対策としての可能性から関心を集めている。
- PRISMAガイドラインと事前登録(PROSPERO CRD42023444511)に従い、習慣的な寒冷暴露下で生活する北極圏成人のBAT活性の証拠を記述することを目的とした系統的レビューが行われた。
- PubMed、Embase、Scopusを2024年11月時点で系統的に検索し、治験登録検索、参考文献リストの手動スクリーニング、専門家への照会も行った。
- 研究選択に関する制限は設けなかった。各研究は、観察的コホート研究と断面研究のためのNIH品質評価ツールを用いて評価された。
- 429件の研究をスクリーニングした結果、21件の全文が適格性評価に含まれ、8件の研究が包含基準を満たした。
- 含まれた研究の異質性のため、メタ分析は行われなかった。
- 結果は、寒冷暴露後の鎖骨上皮膚温度の上昇、甲状腺ホルモン動態、BATに関連する遺伝マーカーによって裏付けられるように、北極圏集団ではBAT活性が高いことを示している。
- 知見は、北極圏地域に住む成人における寒冷適応におけるBATの役割を強調しているが、方法論的な限界が残っており、さらなる研究が必要である。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40804739
[quote_source]: Motzfeldt Jensen M, Jørgensen MG, Elberling Almasi C and Andersen S. “Effect of habitual cold exposure on brown adipose tissue activity in Arctic adults: a systematic review.” International journal of circumpolar health 84, no. 1 (2025): 2545059.
監修者情報
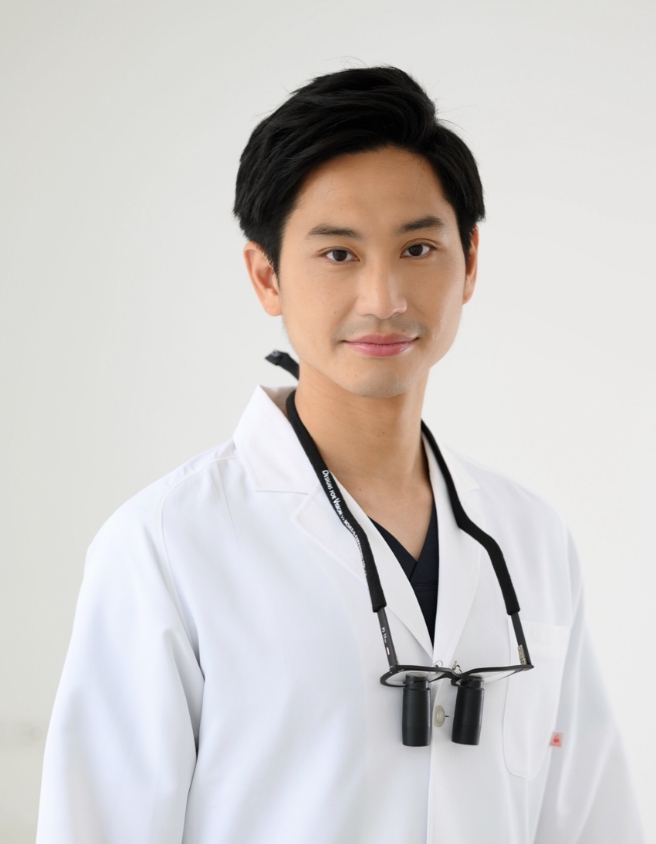
牧野歯科・矯正歯科 歯科医師
牧野 盛太郎Seitaro Makino
略歴
所属学会
- 日本口腔外科学会認定医
- 日本再生医療学会認定医
- 日本口腔外科学会
- 日本再生医療学会
- 日本顎顔面インプラント学会
- 日本口腔インプラント学会