ブログ
季節の変わり目で口の中がネバネバする。これはドライマウス?
秋風が心地よい季節、肌の乾燥とともにお口の乾燥も気になりませんか。「口の中がネバネバする」「会話中に舌がもつれる」といった症状は、唾液が減る「ドライマウス」のサインかもしれません。
実は、日本では約800万人の患者がいるとされ、成人の4人に1人が悩んでいる可能性のある、非常に身近な症状です。単なる不快感と軽視しがちですが、放置すると虫歯や歯周病、さらには誤嚥性肺炎といった深刻な病気のリスクを高めることもあります。
この記事では、ドライマウスの様々な原因から、今日からすぐに始められるセルフケア、そして専門的な治療法までを詳しく解説します。ご自身の状態と向き合い、つらい症状を改善する第一歩にしてください。
口のネバネバや舌の痛みは危険信号?セルフチェックリスト
ドライマウスは、単に口が渇くだけの症状ではありません。 唾液は、お口の健康を守るために、以下のような重要な役割を担っています。
- 潤滑作用
- 食べ物をスムーズに飲み込んだり、会話を滑らかにしたりします。
- 自浄作用
- 食べカスや細菌を洗い流し、お口の中を清潔に保ちます。
- 抗菌作用
- 細菌の増殖を抑え、虫歯や歯周病、口臭を防ぎます。
- 粘膜保護・修復作用
- お口の粘膜を潤して刺激から守り、傷の治りを助けます。
- 消化作用
- 食べ物に含まれるデンプンを分解し、消化を助けます。
唾液が減るとこれらの働きが低下し、様々な不快症状が現れます。 ご自身の状態を把握するため、以下の項目をチェックしてみましょう。
【ドライマウス・セルフチェックリスト】
- 口の中が乾いて、ネバネバするように感じる
- パンやクッキーなど、水分の少ない食べ物が飲み込みにくい
- 食事の時に、飲み物で流し込むことが多い
- 舌の表面がひび割れていたり、ヒリヒリと痛んだりする
- 以前よりも口臭が強くなった気がする
- 食べ物の味が分かりにくい、味が変わったと感じる
- 夜中に口の渇きで目が覚めてしまう
- 長時間、話し続けることがつらい
- 入れ歯が安定せず、歯ぐきに当たって痛む
これらの項目に2〜3個以上当てはまる場合、ドライマウスが疑われます。 唾液の減少は、虫歯や歯周病、口内炎のリスクを高めるため、 早めに原因を探り、対策を始めることが重要です。
加齢やストレス、服用中の薬が原因の場合
ドライマウスはなぜ起こるのでしょうか。原因は多岐にわたりますが、 特に日常生活に潜む代表的な原因として、以下の3つが挙げられます。
- 加齢による変化 年齢を重ねると、唾液を作る「唾液腺」の機能が少しずつ低下します。 また、食事を噛む力や飲み込む力など、口周りの筋力が衰えることも、 唾液の分泌量を減らす一因と考えられています。
- ストレスや緊張 唾液の分泌は、自律神経によってコントロールされています。 リラックス時に優位になる「副交感神経」はサラサラの唾液を、 緊張・興奮時に優位になる「交感神経」はネバネバの唾液を分泌させます。 過度なストレスで交感神経が優位な状態が続くと、口の渇きやネバつきを感じやすくなります。
- 薬の副作用 特定の病気の治療で服用している薬が、原因となることも少なくありません。 降圧剤(血圧の薬)、抗ヒスタミン薬(アレルギーの薬)、抗うつ薬、 鎮痛薬など、多くの薬で副作用として口の渇きが報告されています。 もし服用中の薬に心当たりがある場合でも、自己判断で中断するのは危険です。 必ず処方した医師や薬剤師に相談してください。
マスク生活で悪化する口呼吸の罠
長引いたマスク生活は、私たちの呼吸法に思わぬ影響を与えました。 マスクによる息苦しさから、無意識に口で呼吸する「口呼吸」です。
本来、呼吸は鼻で行うのが理想的です。 鼻呼吸では、吸った空気が鼻腔を通る際に適切に加湿・加温されます。 しかし、口呼吸では冷たく乾いた空気が直接お口の中に入り込み、 大切な唾液をどんどん蒸発させてしまいます。
口呼吸が習慣化すると、ドライマウスだけでなく、以下のような問題も起こりやすくなります。
- 虫歯・歯周病の悪化
- 唾液の自浄作用が低下し、お口の中で細菌が繁殖しやすくなります。
- 口臭の発生
- 細菌の繁殖により、不快な口臭が強くなることがあります。
- 免疫力の低下
- ウイルスや細菌が直接喉に届きやすくなり、感染症のリスクが上がります。
朝起きた時に、喉がカラカラに乾いている方は要注意です。 睡眠中に口呼吸になっている可能性が高いサインと言えるでしょう。
唾液の質を変える食生活や生活習慣
唾液の量や質は、日々の食生活や生活習慣に大きく影響されます。 お口の潤いを保つためには、意識的な習慣の見直しが効果的です。
まず基本は、こまめな水分補給です。 体内の水分が不足すれば、唾液の材料も不足し、分泌量は減ってしまいます。 ただし、カフェインを含むコーヒーや緑茶、アルコール類は注意が必要です。 これらには利尿作用があるため、水分補給のつもりが逆に脱水を招くことがあります。 水分補給の基本は、水やカフェインの少ない麦茶などを選ぶことです。
食事の仕方も、唾液の分泌に大きく関わっています。 食べ物をよく噛む「咀嚼(そしゃく)」は、唾液腺を直接刺激し、 唾液の分泌を促す最も自然で効果的な方法の一つです。 柔らかい食事だけでなく、少し歯ごたえのある食材を取り入れ、 一口30回を目安によく噛むことを意識してみてください。
また、喫煙習慣は口腔内の血行を悪化させ、唾液腺の働きを低下させます。 健康な唾液を十分に分泌させるためにも、禁煙を検討することが望ましいです。
シェーグレン症候群や糖尿病など他の病気の可能性
セルフケアを試しても症状が改善しない場合、注意が必要です。 その口の渇きは、何らかの病気が原因で起きているサインかもしれません。
特に注意したい病気の一つが「シェーグレン症候群」です。 これは、本来体を守るはずの免疫システムが異常をきたし、 自分自身の唾液腺や涙腺などを攻撃してしまう自己免疫疾患です。 唾液腺がリンパ球によって攻撃されると機能が低下し、 その結果として重度のドライマウスやドライアイ症状が現れます。
シェーグレン症候群の影響は腺組織だけにとどまりません。 関節痛や倦怠感といった全身症状を伴うこともあります。 さらに、全身の臓器に影響を及ぼし、非ホジキンB細胞リンパ腫という 血液のがんを発症するリスクを高める可能性も指摘されています。 現在の治療は、症状を和らげる対症療法が中心となっています。
また、「糖尿病」もドライマウスを引き起こす代表的な病気です。 血糖値が高い状態が続くと、体は余分な糖を尿として排出しようとします。 その際に多くの水分が一緒に失われるため、体は脱水傾向になり、 強い口の渇き(口渇)を感じるようになります。
その他、腎臓の病気や高血圧などが原因となることもあります。 長く続く頑固な口の渇きは、放置せずに原因を突き止めることが重要です。 まずは、かかりつけの歯科や内科などの医療機関に相談しましょう。
今日から始められる!ドライマウスを和らげるセルフケア4選
口の中のネバつきや渇きは、会話や食事の妨げとなり、生活の質(QOL)を大きく下げてしまいます。 専門的な治療が必要な場合もありますが、まずはご自身で症状を和らげる工夫を試すことが大切です。
これからご紹介するのは、誰でも今日からすぐに始められる簡単なセルフケアです。 唾液の分泌を促す、お口の潤いを補うなど、様々な角度からアプローチします。 ご自身の生活に取り入れやすいものから試してみて、つらい症状の緩和を目指しましょう。
唾液の分泌を促す「唾液腺マッサージ」と舌の運動
唾液は、お口の潤いを保つだけでなく、細菌の増殖を抑え、粘膜を保護する重要な役割を担っています。 唾液腺を直接刺激したり、口周りの筋肉を動かしたりすることで、唾液の分泌を効果的に促せます。 特に食事の前に行うと、食べ物の消化を助けることにもつながり、一石二鳥です。
■ なぜ効果があるの?唾液腺マッサージの仕組み
お口の周りには、「耳下腺(じかせん)」「顎下腺(がっかせん)」「舌下腺(ぜっかせん)」という3つの大きな唾液腺があります。 これらを優しくマッサージすることで、唾液腺に物理的な刺激が加わり、唾液の産生と分泌が促されます。 また、血行が良くなることで、唾液腺の機能活性化も期待できます。
【具体的なマッサージ方法】
痛みを感じない、気持ち良い程度の力加減で行いましょう。各10回程度が目安です。
- 耳下腺マッサージ
- 耳の前、上の奥歯あたりにある最大の唾液腺です。
- 人差し指から小指の4本を頬にあて、後ろから前へ円を描くように優しく回します。
- 顎下腺マッサージ
- 顎の骨の内側にある、柔らかい部分の唾液腺です。
- 親指を顎の骨の内側にあて、耳の下から顎の先まで数カ所を順番に優しく押します。
- 舌下腺マッサージ
- 舌の真下、顎の先のとがった部分の内側にある唾液腺です。
- 両手の親指をそろえて顎の下にあて、舌を押し上げるようにゆっくりと圧迫します。
■ 舌の運動で口周りの筋肉を活性化
舌や口周りの筋肉(口腔周囲筋)を意識的に動かすことも、唾液腺への良い刺激となります。 デスクワークの合間やリラックスタイムに、ぜひ取り入れてみてください。
- 舌を思いきり前に突き出し、数秒間キープする。
- 突き出した舌を、左右の口角にゆっくりと交互に動かす。
- 口を閉じた状態で、舌を使って歯茎の表側をなぞるように、ゆっくりと一周させる(右回り・左回り)。
これらのマッサージや運動を毎日の習慣にすることで、唾液が出やすい状態を維持しやすくなります。
食事で摂りたい食べ物と避けるべき飲み物
毎日の食事は、唾液の分泌をコントロールする絶好の機会です。 食べ物や飲み物の選び方を少し工夫するだけで、ドライマウスの症状緩和が期待できます。
■ 唾液分泌を促す!積極的に摂りたい食べ物
唾液は、食べ物をよく噛む「咀嚼(そしゃく)」という行為によって、反射的に分泌が促されます。 そのため、自然と咀嚼回数が増える食品を意識して取り入れるのがおすすめです。
| おすすめの食品 | 理由 | 具体例 |
| 噛み応えのある食品 | 咀嚼による機械的な刺激が、唾液腺の働きを直接的に活性化させます。 | ごぼう、れんこんなどの根菜類、きのこ類、こんにゃく、海藻類 |
| 酸味のある食品 | 酸味による味覚刺激が、自律神経(副交感神経)を介して唾液分泌を強力に促します。 | 梅干し、レモン、グレープフルーツ、酢の物 |
| 粘り気のある食品 | ムチンなどの成分が、口腔粘膜の保湿や保護に役立つと考えられています。 | 納豆、オクラ、山芋、なめこ |
■ 要注意!お口の乾燥を招きやすい飲み物
一方で、飲み物の中には、かえってお口の乾燥を悪化させてしまうものもあります。
- カフェインを含む飲料
- コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなど。
- カフェインには利尿作用があるため、体内の水分が尿として排出されやすくなります。
- アルコール飲料
- アルコールにも利尿作用があり、分解する過程で水分を消費するため、脱水傾向になります。
- 糖分の多い飲料
- ジュースやスポーツドリンクなど。
- 口の中の浸透圧を高め、かえって渇きを感じさせたり、口内をネバつかせたりします。
水分補給の基本は「水」または「麦茶」などのノンカフェイン飲料です。 一度にがぶ飲みするのではなく、30分に一度など、時間を決めてこまめに飲む習慣をつけましょう。
保湿ジェル・スプレー・洗口液の効果的な選び方と使い方
唾液の分泌を促すセルフケアと並行して、口腔保湿剤でお口の潤いを直接補うことも非常に有効です。 保湿剤には様々なタイプがあるため、ご自身の症状や生活スタイルに合わせて賢く使い分けましょう。
■ 口腔保湿剤の種類と特徴
- ジェルタイプ
- 保湿効果の持続時間が比較的長いのが特徴です。指やスポンジブラシで口腔粘膜(頬の内側、上あご、舌)にまんべんなく塗り広げます。特に乾燥しやすい就寝前の使用が効果的です。
- スプレータイプ
- 霧状の保湿剤で、気になった時にいつでも手軽に使えます。持ち運びに便利で、外出先や会話の前など、即時的に潤いが欲しい場面で活躍します。
- 洗口液(マウスウォッシュ)タイプ
- 口をすすぐことで、お口全体を一度に保湿・浄化できます。毎日の歯磨きの仕上げとして取り入れると、手軽に保湿ケアができます。
■ 医師が教える!選び方と使い方のポイント
- 刺激の少ない製品を選ぶ
- ドライマウスの方は粘膜が敏感なことがあるため、アルコールフリーなど刺激の少ない製品を選ぶことが推奨されます。香料や甘味料などの添加物が少ない、低刺激性の製品を選びましょう。
- 保湿成分に注目する
- ヒアルロン酸、ベタイン、コラーゲン、リピジュア®といった保湿成分が配合されている製品は、潤いを長時間キープしやすい傾向にあります。
- 使用タイミングを意識する
- 就寝前、起床時、食事の前、会話の前、薬を飲む前など、乾燥が気になるタイミングでこまめに使用することが、効果を高めるコツです。
これらの保湿剤は、不快な症状を和らげる対症療法ですが、QOLを維持するために非常に役立ちます。
就寝中の乾燥を防ぐ工夫(加湿器・鼻呼吸テープなど)
「朝起きると口の中がカラカラ」「夜中に喉の渇きで目が覚める」といった悩みはありませんか。 睡眠中は生理的に唾液の分泌量が減るうえ、無意識に口呼吸になりやすく、乾燥が悪化しやすい時間帯です。 いくつかの工夫で、睡眠中の不快な乾燥を効果的に防ぎましょう。
■ まずは寝室の環境を見直す
- 加湿器で湿度をコントロール
- 空気が乾燥する季節は、加湿器を使いましょう。寝室の湿度を50~60%に保つことで、呼吸による口腔内からの水分蒸発を抑えられます。濡れタオルを室内に干すだけでも一定の効果があります。
- マスクの着用
- 就寝時にマスクを着けると、ご自身の呼気に含まれる湿気がマスク内にこもり、口や喉の周りの湿度を高く保つことができます。保湿用の濡れマスクなども市販されています。
■ 乾燥の元凶「口呼吸」を「鼻呼吸」へ
口呼吸は、乾いた空気が直接粘膜に当たり、唾液を蒸発させる最大の原因の一つです。
- 鼻呼吸テープを活用する
- 唇に専用のテープを貼り、物理的に口が開きにくくすることで、鼻呼吸を促します。ただし、鼻炎やアレルギーなどで鼻が詰まっている場合は、呼吸が苦しくなるため使用を避けてください。
- 枕の高さを調整する
- 枕が高すぎると気道が狭くなり、口呼吸を誘発することがあります。ご自身に合った高さの枕を見直すことも、間接的なドライマウス対策になります。
シェーグレン症候群のような自己免疫疾患が背景にある場合、唾液腺自体の機能が低下しているため、特に夜間の乾燥症状が強く現れることがあります。 これらのセルフケアを丁寧に試しても症状が改善しない場合は、他の病気が隠れている可能性も考えられます。 その際は、自己判断で様子を見続けず、専門の医療機関に相談することをおすすめします。
症状が続くなら専門家へ!医療機関で行う検査と治療法
セルフケアを数週間続けても、一向に口の渇きやネバつきが改善しない。 むしろ症状が強くなっているようで不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。 つらい症状が続く場合、単なる乾燥ではなく病気が隠れている可能性があります。
自己判断で放置せず、専門家である医療機関に相談することが非常に重要です。 医療機関では、症状の原因を正確に突き止めるための客観的な検査を行います。 そして、検査結果に基づき、一人ひとりの状態に合った専門的な治療を受けられます。
まずは何科を受診?歯科・口腔外科・内科の選び方
「ドライマウスで病院へ」と思っても、何科を受診すればよいか迷うでしょう。 受診すべき診療科は、口の渇き以外にどのような症状があるかで変わります。 以下の表を目安に、ご自身の状態に最も近い診療科を選んでみてください。
| 診療科 | このような症状がある場合におすすめ |
| 歯科・口腔外科 | 口の渇きに加えて、虫歯の増加、歯周病の悪化、口内炎、舌の痛み、入れ歯が合わないなど、お口の中のトラブルが中心の場合。まずはお口の専門家である歯科に相談するのが一般的です。 |
| 耳鼻咽喉科 | 慢性的な鼻づまりがあり、無意識に口呼吸をしている自覚がある場合。アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎など、鼻の病気がドライマウスの原因となっている可能性があります。 |
| 内科・リウマチ科 | 口の渇きだけでなく、目の渇き(ドライアイ)、関節の痛み、全身の倦怠感など、他の症状もある場合。シェーグレン症候群などの自己免疫疾患や糖尿病が疑われます。また、服用中の薬の副作用が原因と考えられる場合も、まずは処方元の医師への相談が基本です。 |
どの科を受診すべきか判断に迷う場合は、まずかかりつけの歯科医院に相談し、 必要に応じて専門の医療機関を紹介してもらうのも良い方法です。
唾液分泌量の測定や血液検査などの具体的な検査内容
医療機関では、ドライマウスの原因や重症度を客観的に評価するため、 いくつかの検査を組み合わせて診断を進めます。
- 問診・視診
- 症状がいつからあるか、生活習慣、服用薬、既往歴などを詳しく伺います。
- その後、歯科医師が直接お口の中を診て、粘膜や舌の乾燥状態、
- 虫歯や歯周病の有無、舌苔(ぜったい)の付着具合などを確認します。
- 唾液分泌量測定
- 唾液がどのくらい出ているかを調べる、シンプルで重要な検査です。
- ガムなどを一定時間噛み、その間に出る唾液の量を測定します。
- 「ガムテスト」や「サクソンテスト」と呼ばれ、刺激時の分泌能を評価します。
- 血液検査
- 全身の病気が疑われる場合に行われます。特に重要なのが自己免疫疾患です。
- シェーグレン症候群の検査
- 本来体を守る免疫が自分自身を攻撃する病気で、血液検査で特徴的な
- 「自己抗体」の有無を調べます。特に「抗SS-A/Ro抗体」や
- 「抗SS-B/La抗体」は重要で、シェーグレン症候群の患者さんの
- 約70%で抗Ro抗体が検出されるという報告もあります。
- この抗体は診断の助けになるだけでなく、どのような全身症状が
- 出やすいかの指標にもなります。
- 糖尿病の検査
- 血糖値や過去1~2ヶ月の血糖の状態を反映するHbA1c(ヘモグロビンA1c)を測定します。
- その他の専門的な検査
- 診断を確定するために、唾液腺の働きを画像で評価する検査や、
- 下唇の組織を少量採取して顕微鏡で調べる検査(口唇小唾液腺生検)を
- 行うこともあります。
保湿剤や唾液分泌促進薬などを用いた専門的な治療法
検査で原因や状態が明らかになったら、それに合わせた治療を開始します。 治療は、原因となっている病気の治療と、つらい症状を和らげる対症療法を 組み合わせて進めるのが基本です。
- 原因となっている病気の治療
- 薬の副作用が原因なら、処方医と連携して薬の変更や調整を検討します。
- 糖尿病であれば、食事療法や運動療法、薬物療法による血糖コントロールが
- ドライマウスの改善にもつながります。
- 症状を和らげる対症療法
- 口腔保湿剤の使用:
- ジェルやスプレータイプの保湿剤で、乾燥した粘膜を直接潤して保護します。
- 唾液分泌促進薬:
- 唾液腺の働きを刺激し、唾液の分泌そのものを増やす内服薬です。
- 漢方薬:
- 患者さん一人ひとりの体質に合わせて、体の内側から潤いを補う
- 漢方薬が効果的な場合もあります。
- 口腔保湿剤の使用:
シェーグレン症候群のような自己免疫疾患が原因の場合、 現在の治療は症状を和らげる対症療法が中心です。 しかし、近年では研究が進み、病気の根本的なメカニズムである 免疫の調節異常に働きかける新しい治療薬(バイオ医薬品など)の開発が進んでいます。 将来的には、腺機能の回復や全身症状の軽減といった、より根本的な治療の選択肢が広がることが期待されています。
放置が招く虫歯・歯周病・誤嚥性肺炎のリスク
「ただ口が乾くだけ」と軽く考えてドライマウスを放置してしまうと、 お口の中だけでなく、全身の健康にまで深刻な影響を及ぼす可能性があります。 唾液が持つ、お口と体を守る力が失われることの重大さを知っておきましょう。
| 唾液の主な働き | 唾液が減ると起こる深刻な問題 |
| 自浄・抗菌作用 | 食べかすや細菌が洗い流されず、虫歯や歯周病が急激に進行します。口臭も強くなり、口腔カンジダ症というカビの感染症も起こりやすくなります。 |
| 粘膜保護・修復作用 | 粘膜が直接刺激にさらされ、ヒリヒリとした痛みや口内炎が頻発します。食事を摂ること自体が苦痛になり、味も感じにくくなることがあります。 |
| 消化・潤滑作用 | 食べ物をうまくまとめられず、飲み込みにくくなります。これが、命に関わる「誤嚥(ごえん)」のリスクを高めます。 |
特に注意すべきリスクは以下の通りです。
- 虫歯・歯周病の悪化
- 細菌が繁殖しやすくなるため、虫歯や歯周病が急速に進行します。
- 特に、歯の根元に多発する虫歯はドライマウスの典型的な症状です。
- 口腔カンジダ症
- 口の中に普段からいるカンジダ菌というカビが異常に増殖し、
- 舌が白くなったり、粘膜がヒリヒリと痛んだりします。
- 誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)
- 食べ物や唾液が誤って気管に入ってしまう「誤嚥」が起こりやすくなります。
- その際、口の中で増殖した細菌が一緒に肺へ入り込むことで肺炎を起こします。
- 高齢者だけでなく、体力が落ちている方にとっても命に関わる病気です。
お口の健康は、食事や会話を楽しむといった生活の質(QOL)に直結します。 そして、全身の健康を守るための重要な入り口です。 気になる症状があれば放置せず、できるだけ早く専門家に相談しましょう。
まとめ
口の中のネバつきや渇きは、単なる不快な症状ではなく、お口の健康を守る大切な唾液が減っているサインです。
原因は乾燥やストレス、生活習慣など様々なので、まずは記事でご紹介した唾液腺マッサージや保湿剤の活用といったセルフケアを、ご自身の生活に取り入れてみてください。
しかし、セルフケアを続けても改善しない場合や、目の渇きや関節痛など他の不調も伴う場合は、シェーグレン症候群や糖尿病といった病気が隠れている可能性も考えられます。
放置すると虫歯や歯周病のリスクが高まるだけでなく、全身の健康にも影響します。「ただの乾燥」と軽視せず、つらい症状が続く場合は、ぜひ早めに歯科や内科などの専門家へ相談しましょう。
参考文献
[title]: Advanced strategies for targeting molecular pathways in Sjögren’s syndrome.
【要約】
- シェーグレン症候群(SS)は、非常に攻撃的で慢性的な性質を持つ、リウマチ性疾患の中でも独特な疾患であり、主に外分泌腺に影響を与え、口渇やドライアイなどの症状を引き起こす。
- しかし、その影響は分泌不全にとどまらず、他の臓器系にも影響を及ぼし、非ホジキンB細胞リンパ腫の可能性を高める。
- 近年の研究により、遺伝的脆弱性、唾液腺における拡張免疫反応、そして1型インフルエンザ経路の役割が明らかになり、その病態生理学的理解が深まっている。
- SSの病態生理を標的とする新たなバイオ医薬品や低分子化合物が、医薬品開発パイプラインで進歩している。
- 本レビューは、腺機能の回復と全身的な疾患負担の軽減を目指した新たな治療戦略、そして原発性シェーグレン症候群の病因に関する最近の進歩に焦点を当てている。
- 本研究は文献の批判的レビューを通じて、SSにおける免疫異常の中心的な役割を強調し、バイオ医薬品や標的分子介入を含む新たな治療戦略を探求している。
- 統合的な治療アプローチを提唱し、臨床研究において腺以外の症状に対処する必要性を強調している。
- 本レビューは、SSの病態発生に関するより深い理解に貢献し、将来の治療的進歩の基礎を提供する。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40619026
[quote_source]: Wang D, Liu Y, Lu X and Xu F. “Advanced strategies for targeting molecular pathways in Sjögren’s syndrome.” Biochemical pharmacology 241, no. (2025): 117116.
[title]: Regulatory T cell therapy for Sjögren’s disease: From pathogenesis to targeted treatment.
【要約】
- シェーグレン症候群(SjD)は、唾液腺と涙腺へのリンパ球浸潤を特徴とする慢性全身性自己免疫疾患であり、ドライアイとドライマウスという特徴的な症状を引き起こします。
- 腺機能不全以外にも、多くの患者がB細胞の過活動、臓器特異的炎症、非ホジキンリンパ腫のリスク著しく増加などの全身的合併症を経験しますが、これらはしばしば認識不足であり、適切な管理がなされていません。
- 現在の治療法は、主に経験的かつ対症療法であり、疾患の進行を抑制したり、免疫寛容を回復させたりする効果は限定的です。
- 最近の進歩により、自然免疫と獲得免疫の両方に深刻な調節異常があることが明らかになり、I型インターフェロンシグナル伝達、B細胞活性化、コ刺激経路など、臨床試験で現在検討されている新たな治療標的が明らかにされています。
- この調節異常の中心にはT細胞駆動性の病態があり、CD8+T細胞の細胞傷害性、制御性T細胞(Treg)機能の欠損、HLAクラスIIを介した自己抗原の自己反応性CD4+T細胞への提示は、疾患の開始と持続における主要なメカニズムです。
- 増加する証拠は、Ro自己抗原(Ro60とRo52)をSjD発症の中心的な標的として示唆しています。
- 抗Ro抗体は約70%の患者に存在し、診断マーカーと全身的病変の指標の両方として機能します。
- Ro抗原とその対応する抗体は、炎症を起こした唾液組織で一貫して検出され、抗原特異的療法の有望な標的としての可能性を強調しています。
- 本稿では、SjDにおけるRo特異的T細胞応答の免疫病理学的役割を検討し、遺伝子操作されたTregベースの療法がどのように精密な免疫調節を可能にし、寛容を回復させ、この複雑な自己免疫疾患の患者に持続的な疾患制御を提供できるかを概説しています。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40978495
[quote_source]: Lim ZFS, Hoi AY, Vincent FB, Ooi JD, Morand EF, Rischmueller M and Ting YT. “Regulatory T cell therapy for Sjögren’s disease: From pathogenesis to targeted treatment.” Journal of translational autoimmunity 11, no. (2025): 100311.
監修者情報
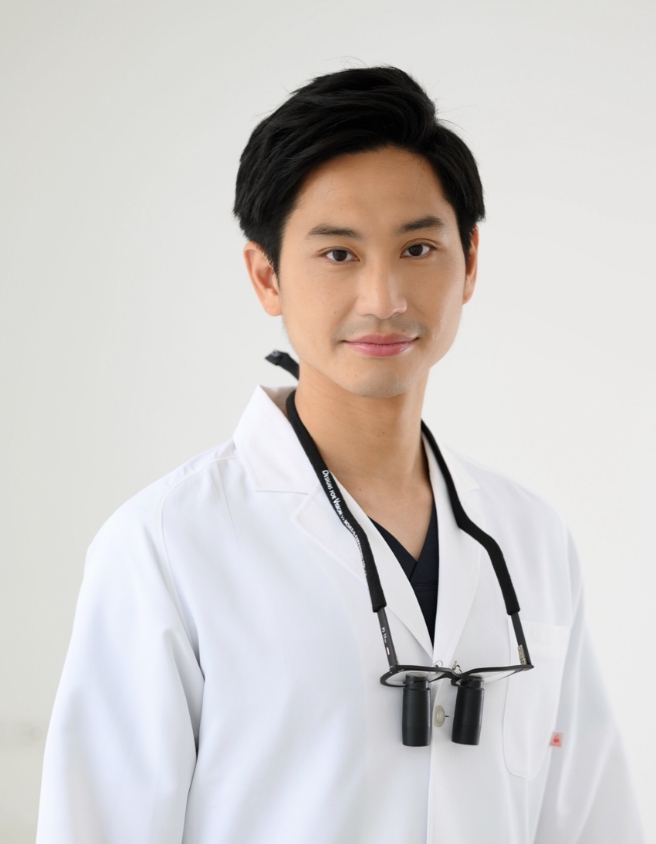
牧野歯科・矯正歯科 歯科医師
牧野 盛太郎Seitaro Makino
略歴
所属学会
- 日本口腔外科学会認定医
- 日本再生医療学会認定医
- 日本口腔外科学会
- 日本再生医療学会
- 日本顎顔面インプラント学会
- 日本口腔インプラント学会