ブログ
季節の変わり目で体調を崩しやすく顎がだるい。これって顎関節症?
季節の変わり目に悪化?顎関節症の主な症状と原因4つ
季節の変わり目は、気温や気圧の変化が大きく、心身ともに不調を感じやすい時期です。 「朝起きると顎がだるい」「食事中に顎がカクカク鳴る」といった症状はありませんか。
それは「顎関節症」のサインかもしれません。 顎関節症は、顎の関節やその周りの筋肉(咀嚼筋)に問題が起こる病気の総称です。 生活習慣や噛み合わせなど原因は様々ですが、特に季節の変わり目は症状が出やすい時期です。 ここでは、顎関節症の代表的な症状と、その背景にある4つの主な原因を詳しく解説します。
口が開かない、カクカク音が鳴るなどの代表的な症状
顎関節症の症状は多岐にわたりますが、特に代表的なものが以下の3つです。 これらの症状は1つだけ現れることもあれば、複数が同時に現れることもあります。
- 顎の関節や筋肉の痛み(顎関節痛・咀嚼筋痛) 食事やあくびなど、口を開け閉めする際に痛みを感じます。 痛む場所は耳の前あたりにある顎関節部や、頬・こめかみにある筋肉などです。 鋭い痛みだけでなく、安静にしていても重だるい鈍い痛みを感じることもあります。 痛みのせいで硬いものが食べられないなど、食事に支障をきたすケースも少なくありません。
- 口が開きにくい(開口障害) 正常な状態では、指を揃えて縦にした人差し指・中指・薬指の3本が入ります。 これは距離にすると約40~50mmに相当します。 しかし、顎関節症になると指が2本程度しか入らないなど、口を大きく開けられなくなります。 急に口が開かなくなる場合もあれば、時間をかけて徐々に開きにくくなる場合もあります。
- 顎を動かしたときの音(関節雑音) 口を開け閉めする際に、耳の前あたりで音がすることがあります。音の種類は大きく分けて2つです。
- クリック音:「カクカク」「コキッ」というような、はっきりとした音です。
- クレピタス音:「ジャリジャリ」「ミシミシ」といった、砂をこするような軋む音です。
音が鳴るだけで痛みがなければ、緊急の治療は必要ない場合もあります。 しかし、顎関節の内部で何らかの変化が起きているサインであることに変わりはありません。
これらの3大症状に加え、頭痛や首・肩のこり、耳鳴り、めまいといった全身症状を伴うこともあります。 一見すると顎とは関係なさそうに思える不調も、実は顎関節症が原因かもしれません。
ストレスによる無意識の食いしばりや歯ぎしり
精神的なストレスは、顎関節症を引き起こす非常に大きな要因です。 私たちはストレスを感じると、無意識のうちに全身の筋肉を緊張させます。 特に、顎を動かす筋肉(咬筋など)は、ストレスの影響を受けやすい部分です。
- 食いしばり(クレンチング) 日中、仕事や勉強に集中している時などに、無意識に上下の歯を強く噛みしめる癖です。 本来、リラックスしている状態では上下の歯は触れ合わず、わずかな隙間が空いています。 この無意識の癖は「TCH(Tooth Contacting Habit:歯列接触癖)」とも呼ばれ、自覚がない方がほとんどです。
- 歯ぎしり(ブラキシズム) 主に睡眠中に、歯をギリギリとこすり合わせたり、強く噛みしめたりする行為を指します。 歯ぎしりの際に顎にかかる力は、食事の時よりもはるかに強く、歯や顎の関節に甚大な負担をかけます。
季節の変わり目は、異動や転勤といった環境の変化だけでなく、寒暖差自体が体へのストレスとなります。このようなストレスが引き金となり、食いしばりや歯ぎしりが増えてしまうのです。 結果として顎周りの筋肉が常に疲労し、顎関節に過剰な力がかかり続け、痛みや開口障害といった症状が現れます。
気圧の変化と自律神経の乱れが顎に与える影響
「天気が悪くなると古傷が痛む」という話があるように、顎関節症も気圧の変化で悪化することがあります。これには、体の調子を24時間体制で調整している「自律神経」が深く関わっています。
自律神経は、体を活動的にする「交感神経」と、リラックスさせる「副交感神経」から成り立っています。この2つの神経がシーソーのようにバランスを取ることで、私たちの体は健康な状態を保っています。
しかし、台風の接近などで気圧が急激に低下すると、体はこれを一種のストレスと捉え、交感神経が優位になります。 交感神経が活発になると、顎関節に以下のような影響が及びます。
| 交感神経が優位になった際の変化 | 顎関節への具体的な影響 |
| 血管が収縮する | 顎周りの筋肉の血行が悪化し、筋肉が硬直しやすくなる。 |
| 筋肉が緊張する | 無意識の食いしばりを誘発し、顎関節への負担が増加する。 |
| 痛みに敏感になる | 普段は気にならない程度の顎の違和感を、痛みとして強く感じるようになる。 |
季節の変わり目は、低気圧と高気圧が頻繁に入れ替わるため、気圧の変動が大きくなります。 この環境の変化が自律神経の乱れを招き、顎の筋肉の緊張や痛みを引き起こすのです。 これが、季節の変わり目に顎関節症の症状が悪化しやすい理由の一つです。
顎関節症か自分でわかるセルフチェックリスト
ご自身の顎の不調が顎関節症によるものか、以下の項目でチェックしてみましょう。 ただし、これはあくまで簡易的な目安です。正確な診断のためには、必ず専門の医療機関を受診してください。
【顎の動きと音に関するチェック】
- まっすぐ口を開けたとき、人差し指・中指・薬指の3本が縦にすっと入らない。
- 口を大きく開け閉めすると、顎が左右のどちらかにずれる、または蛇行する。
- 口を開け閉めする際に、耳の前あたりで「カクカク」「コキッ」という音が鳴る。
- 口を動かすと「ジャリジャリ」「ミシミシ」といった砂をこするような音がする。
【痛みやだるさに関するチェック】
- 硬いものを食べた後や、食事の後に顎が疲れる、または痛む。
- 朝起きたときに、顎や頬のあたりにこわばりやだるさを感じる。
- 何もしていないのに、顎やこめかみに鈍い痛みがある。
- あくびをしたり、リンゴを丸かじりしたりすると痛む。
【生活習慣や他の症状に関するチェック】
- 日中、気づくと上下の歯を噛みしめていることがある。
- 家族やパートナーから、寝ている間の歯ぎしりを指摘されたことがある。
- 原因のわからない頭痛や首・肩のこりが続いている。
- 耳鳴りや、耳が詰まったような感じがすることがある。
これらの項目に1つでも当てはまる場合は、顎関節症の可能性があります。 特に複数の項目に当てはまる方は、症状が進行していることも考えられます。 気になる症状があれば、放置せずに早めに歯科や口腔外科を受診することをおすすめします。
今すぐできる!顎の痛みを和らげるセルフケアと専門的な治療法
季節の変わり目に感じる顎のだるさや痛みは、本当につらいものです。 食事や会話といった日常の何気ない動作にも影響が出て、気分まで落ち込んでしまう方も少なくありません。
治療には、ご自身で始められるセルフケアと、クリニックなどの医療機関で行う専門的な治療法があります。
セルフケアは症状緩和に役立ちますが、根本的な原因解決には専門的な診断が不可欠です。 ここでは、それぞれの具体的な方法について詳しく解説していきます。 ご自身の症状と照らし合わせながら、できることから試してみてください。
筋肉をほぐす簡単マッサージとストレッチの方法
顎関節症の痛みの多くは、顎を動かす筋肉(咀嚼筋)の緊張やこわばりが原因です。 無意識の食いしばりなどで疲労した筋肉を優しくほぐすと血行が促進されます。 その結果、筋肉に溜まった疲労物質が排出されやすくなり、痛みの緩和が期待できます。
ただし、以下の場合はマッサージを避け、まず医療機関を受診してください。
- 何もしなくてもズキズキと強く痛む(急性炎症の可能性)
- 顎の関節部分に熱感や腫れがある
- 無理に動かすと症状が悪化する
1.咀嚼筋マッサージ
入浴中や蒸しタオルで顎周りを温めた後など、体がリラックスしている時に行うとより効果的です。
- 咬筋(こうきん)のマッサージ:
- 奥歯を軽く「いー」と噛みしめたときに、頬で硬く盛り上がる筋肉が咬筋です。
- 人差し指、中指、薬指の3本の指の腹を、その筋肉に優しく当てます。
- 「痛いけれど気持ちいい」と感じるくらいの力で、円を描くようにゆっくりほぐします。
- この動作を約1分間続けましょう。
- 側頭筋(そくとうきん)のマッサージ:
- こめかみのあたりで、噛みしめるとピクピクと動く部分が側頭筋です。
- 咬筋と同様に、3本の指の腹を当てます。
- ゆっくりと円を描くように、筋肉全体をほぐしていきます。
- これも約1分間続けましょう。
2.顎のストレッチ
筋肉の柔軟性を高め、関節の動きをスムーズにするための運動です。 痛みを感じない範囲で、ゆっくりと行いましょう。
- 開口ストレッチ:
- 背筋を伸ばし、リラックスした状態で口をゆっくりと開けます。
- これ以上開かないという少し手前で止め、その状態で5秒間維持します。
- ゆっくりと口を閉じ、力を抜きます。この動作を5回繰り返します。
- 下顎の左右・前方運動:
- リラックスした状態で、下顎をゆっくりと真横(右)に動かし、5秒間維持します。
- 中央に戻し、次に左に動かして5秒間維持します。
- 最後に、下顎を「イー」と前に突き出すように動かし、5秒間維持します。
- この一連の運動を3セット行います。
歯科・口腔外科で行うマウスピース(スプリント)療法
セルフケアで改善が見られない場合や、睡眠中の歯ぎしり・食いしばりが原因として強く疑われる場合には、「スプリント療法」が有効な選択肢となります。 スプリントとは、個人の歯型に合わせて作製する、透明な樹脂でできたマウスピースのような装置です。 主に就寝中に上の歯、または下の歯に装着して使用します。
スプリント療法の主な目的
| 目的 | 具体的な効果 |
| 顎関節や筋肉への負担軽減 | 睡眠中の無意識の歯ぎしりや食いしばりから生じる過剰な力をスプリントが受け止め、歯や顎、筋肉を守ります。 |
| 噛み合わせの安定化 | 顎をリラックスした本来の位置に導き、噛み合わせのバランスを整えることで、筋肉の異常な緊張を防ぎます。 |
| 筋肉の緊張緩和 | スプリントを介して噛むことで、顎周りの筋肉が異常に緊張するのを防ぎ、こわばりや痛みを和らげます。 |
スプリントは市販されていません。 歯科医院で精密な歯型をとり、一人ひとりの顎の状態に合わせて作製する医療機器です。 この治療は健康保険が適用されます。
完成後も、定期的に通院して噛み合わせの調整を行うことが非常に重要です。 自己判断で市販のスポーツ用マウスピースなどを使用すると、噛み合わせがさらに不安定になり、かえって症状を悪化させる危険性があるため、使用は避けてください。
痛み止めや筋弛緩薬などを用いる薬物療法
顎の痛みが強く、食事や睡眠などの日常生活に支障が出ている場合には、薬物療法を併用することがあります。 薬物療法は、つらい症状を一時的に抑えることが目的です。 症状を和らげることで、セルフケアやスプリント療法といった根本的な治療にスムーズに取り組めるようにします。
主に使用される薬剤
- 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs): 一般的に「痛み止め」と呼ばれる薬です。 ロキソプロフェンなどがこれにあたります。 顎関節や筋肉の炎症を抑え、痛みを軽減させる効果があります。 まずはこの薬から処方されることが多いです。
- 筋弛緩薬(きんしかんやく): 筋肉の過度な緊張やこわばりを和らげる薬です。 特に、ストレスなどによる食いしばりで顎周りの筋肉が常に張っているような場合に有効です。 眠気が出ることがあるため、服用中の車の運転などには注意が必要です。
- 抗不安薬・抗うつ薬: ストレスや不安が歯ぎしり・食いしばりの大きな原因となっている場合に、補助的に処方されることがあります。 心身のリラックスを促し、無意識下の筋肉の緊張を解きほぐす効果を期待します。
これらの薬は、あくまで症状を緩和するための対症療法です。 根本的な原因の解決にはならないため、必ず医師の指示に従って服用し、他の治療法と組み合わせて進めていくことが大切になります。
顎関節症の治療で受診すべき診療科の選び方
「顎が痛いけれど、何科に行けばいいのかわからない」という方は非常に多くいらっしゃいます。 顎関節症の診断と治療を専門的に行っているのは、主に「歯科」と「口腔外科」です。 どちらを受診すべきか迷った際の選び方の目安をご紹介します。
1.まずは「歯科」または「歯科口腔外科」へ
基本的に、顎関節症が疑われる場合は、まずお近くの歯科医院を受診するのが第一選択となります。
- 一般歯科: かかりつけの歯科医院があれば、まずはそちらに相談しましょう。 問診や触診、噛み合わせのチェック、症状が軽度であればスプリントの作製など、初期対応が可能です。
- 口腔外科(歯科口腔外科): 「口腔外科」を標榜しているクリニックや、大学病院・総合病院の口腔外科は、より専門的な診療を行っています。 以下のような場合は、口腔外科の受診が推奨されます。 * 痛みが非常に強い * ほとんど口が開かない * 顎の変形が疑われる * 他の歯科医院で改善しなかった
2.症状に応じた他科との連携
顎関節症は、他の身体の不調と関連していることもあります。 歯科・口腔外科での診断の結果、必要に応じて他の診療科との連携が必要になる場合があります。
- 整形外科: 首や肩のこりがひどく、それが顎の痛みに影響していると考えられる場合。
- 耳鼻咽喉科: 耳鳴りやめまい、耳が詰まった感じなど、耳の症状が強い場合。
- 心療内科・精神科: 強いストレスが主な原因と考えられ、不眠や気分の落ち込みなども伴う場合。
まずは歯科・口腔外科で顎の状態を正確に診断してもらうことが、適切な治療への第一歩です。 自己判断で他の診療科を受診する前に、まずは顎の専門家である歯科医師に相談しましょう。
顎関節症を再発させないための生活習慣と予防策
顎関節症のつらい症状が治療で和らいでも、根本的な原因が生活の中に残っていると、季節の変わり目などに症状を繰り返してしまうことがあります。
「もうあの痛みや不快感を経験したくない」と感じる方は、日々の過ごし方を見直すことが再発予防の鍵となります。 顎関節症は、ストレスや無意識の癖など、生活習慣と深く関わる病気です。 ここでは、顎関節症の再発を防ぐための具体的な予防策と、ご自身の生活習慣を見直すポイントを、医師の視点から詳しく解説します。
頬杖やうつ伏せ寝など顎に負担をかける癖の見直し
普段何気なく行っている癖が、実は顎の関節や筋肉に大きな負担をかけている可能性があります。 これらの癖は無意識に行っていることが多いため、まずはご自身の行動を意識することから始めましょう。
特定の方向に長時間、持続的に力が加わることで顎関節のバランスは崩れます。 その結果、痛みや「カクカク」という関節の音につながるのです。
【チェックリスト】顎に負担をかける要注意な癖
ご自身の生活を振り返り、当てはまるものがないか確認してみましょう。
- 頬杖をつく 片側の顎に体重が乗り、関節内部のクッション(関節円板)を圧迫します。
- うつ伏せで寝る、または横向き寝 顎が枕に押し付けられ、長時間にわたり不自然な力が加わります。
- スマートフォンやPCの長時間利用 うつむき姿勢は、頭の重みで首や肩だけでなく、顎周りの筋肉も緊張させます。
- 食事の際の片側噛み 片方の筋肉ばかりが酷使され、筋肉のバランスが崩れる原因になります。
- 硬い食べ物やガムをよく食べる 顎の筋肉を過度に使い、筋肉疲労や関節への負担を増大させます。
- 電話を肩と首で挟む 首から顎にかけての筋肉が強く緊張し、顎関節に悪影響を及ぼします。
これらの癖を改善するには、「意識すること」が第一歩です。 例えば、デスクに「頬杖をつかない」と書いた付箋を貼る、寝るときは仰向けを意識して低い枕を使うなどの工夫が有効です。
ストレスを溜めないリラクゼーション法
ストレスは、顎関節症の大きな引き金となる「食いしばり」や「歯ぎしり」を無意識のうちに増加させます。ストレスを感じると、体を緊張させる交感神経が活発になります。 その結果、顎周りの筋肉がこわばり、顎関節に過度な負担がかかるのです。
心身をリラックスさせ、副交感神経を優位にすることが再発予防に直結します。 日常生活の中で、意識的にリラックスする時間を作りましょう。
日常生活でできるリラクゼーション法
- 腹式呼吸 1. 椅子に深く座り、背筋を軽く伸ばします。 2. 鼻から4秒かけてゆっくり息を吸い込み、お腹を膨らませます。 3. 口から8秒かけてゆっくりと息を吐き出し、お腹をへこませます。 4. この呼吸を数分間繰り返すだけで、心身の緊張が和らぎます。
- 漸進的筋弛緩法(ぜんしんてききんしかんほう) 筋肉の緊張と弛緩を意識的に繰り返すことで、深いリラックス効果が得られます。 1. 顎や肩の筋肉にぐっと力を入れ、5秒ほど緊張させます。 2. その後、一気に力を抜き、筋肉が緩んでいく感覚を20秒ほど味わいます。 3. この動作を他の部位(腕、足など)でも繰り返します。
- ぬるめのお湯での入浴 38~40℃程度のぬるめのお湯に15分以上浸かりましょう。 全身の血行が良くなり、筋肉の緊張が効果的にほぐれます。
放置するリスクと併発しやすい頭痛・肩こりとの関係
「顎が少し痛むだけ」「音が鳴るだけ」と軽く考え、顎関節症を放置してしまうのは非常に危険です。 症状が悪化し、日常生活に大きな支障をきたすだけでなく、全身にさまざまな不調を引き起こすことがあります。
放置することで起こりうること
- 症状の重症化 痛みが慢性化し、口が指2本分も開かなくなる「開口障害」に至ることがあります。
- 食事の困難 硬いものが食べられなくなり、食事が苦痛になります。 重症化すると、栄養摂取に問題が生じるケースも少なくありません。
- 顎関節の変形 長期間の負担により、顎関節の骨が変形してしまうと、元に戻すのは困難です。
特に、原因不明の頭痛や肩こりは、顎関節症と密接に関係している場合が多くあります。 顎を動かす筋肉(咀嚼筋)は、首や肩の筋肉と筋膜で繋がっているためです。 顎の筋肉が異常に緊張すると、その緊張が首や肩にまで波及し、頑固な肩こりや緊張型頭痛を引き起こすのです。
| 関連する部位 | 併発しやすい症状とメカニズム |
| 頭部 | **緊張型頭痛、めまい:**側頭筋の過緊張が、こめかみ周辺の締め付けられるような頭痛を引き起こします。 |
| 首・肩 | **肩こり、首の痛み:**咀嚼筋の緊張が、筋膜を通じて首や肩の筋肉(胸鎖乳突筋、僧帽筋)に伝わります。 |
| 耳 | **耳鳴り、耳の痛み:**顎関節は耳のすぐ前にあるため、関節の炎症や筋肉の緊張が耳の症状として現れることがあります。 |
| 精神面 | **不眠、集中力の低下:**持続的な痛みがストレスとなり、自律神経の乱れを助長し、精神的な不調につながります。 |
顎の不調は、体からの重要なサインです。 放置せずに、早期に適切なケアや治療を受けることが何よりも大切です。
睡眠の質を高めて歯ぎしりを軽減する方法
睡眠中の歯ぎしりや食いしばりは、自分の意識ではコントロールできないため、顎関節症の非常に厄介な原因の一つです。 この無意識の負担を減らす鍵は、「睡眠の質」を高めることにあります。 浅い眠りやストレスを抱えたままの入眠は、歯ぎしりを起こしやすくするためです。
睡眠の質を高めるための具体的な工夫
- 就寝前のルーティンを見直す
- 入浴: 就寝の90分前までに、ぬるめのお湯にゆっくり浸かり、体の深部体温を一度上げることが、自然な眠気を誘います。
- デジタルデトックス: スマートフォンなどが発するブルーライトは脳を覚醒させます。 就寝1時間前には使用をやめ、静かな音楽や読書で過ごしましょう。
- 飲食のコントロール: カフェインやアルコール、就寝直前の食事は睡眠を浅くします。 特に夕食は就寝3時間前までに済ませるのが理想的です。
- 快適な睡眠環境を整える
- 寝具の選択: 仰向けで寝るのが顎への負担が最も少ない姿勢です。 うつ伏せ寝や高すぎる枕は避け、ご自身の首のカーブに合った枕を選びましょう。
- 寝室環境の調整: 部屋を暗く、静かで快適な温度・湿度に保つことが、深い眠りのために重要です。
これらの工夫を試しても歯ぎしりが気になる場合は、歯科医院で睡眠中の顎への負担を軽減する「ナイトガード(マウスピース)」を作製することも有効な手段です。 セルフケアと専門的な治療を組み合わせ、再発しない健やかな状態を目指しましょう。
まとめ
今回は、季節の変わり目に起こりやすい顎のだるさと、その原因である顎関節症について詳しく解説しました。
顎の不調は、ストレスや気圧の変化、頬杖などの何気ない癖が積み重なって起こります。まずは、ご紹介したマッサージや生活習慣の見直しなど、ご自身でできるセルフケアから試してみてください。
しかし、「音が鳴るだけ」「少し痛いだけ」と軽く考えて放置するのは禁物です。顎の不調は、頭痛や肩こりといった全身の症状につながることもあります。気になる症状が続く場合は、一人で悩まず、早めに歯科や口腔外科などの専門家に相談しましょう。適切なケアでつらい症状を和らげ、快適な毎日を取り戻してくださいね。
監修者情報
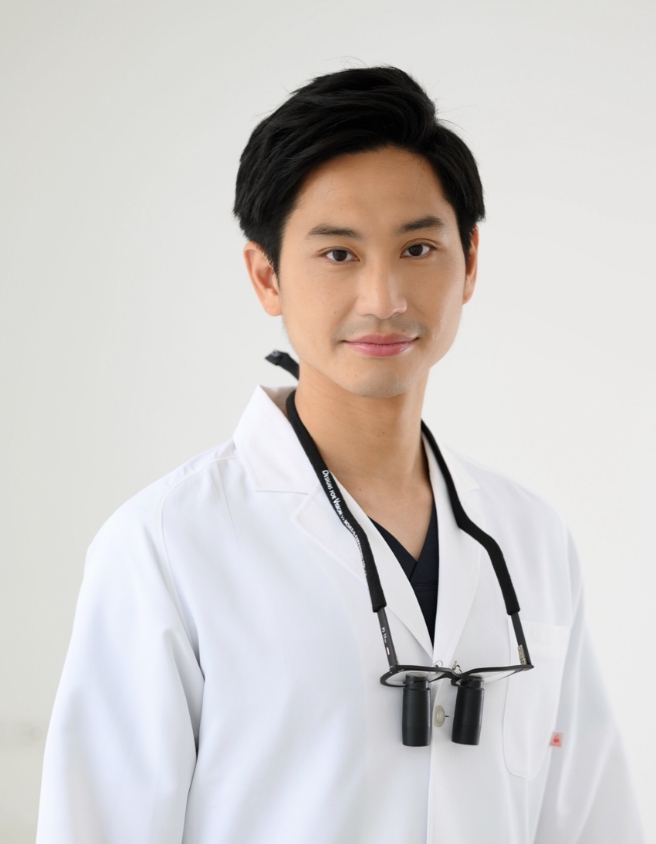
牧野歯科・矯正歯科 歯科医師
牧野 盛太郎Seitaro Makino
略歴
所属学会
- 日本口腔外科学会認定医
- 日本再生医療学会認定医
- 日本口腔外科学会
- 日本再生医療学会
- 日本顎顔面インプラント学会
- 日本口腔インプラント学会