ブログ
口内炎がなかなか治らない場合、どうすれば良いか?
「ただの口内炎だろう」と軽く考えていても、食事のたびにしみる痛みや不快感が長引くと、「何か悪い病気では…」と不安になりますよね。
実は、口の中は全身の健康状態を映し出す「鏡」とも言われ、ほとんどの口内炎は1〜2週間で自然に治ります。もしそれ以上続く場合、その背景には単なる栄養不足だけでなく、重大な病気が隠れている可能性も否定できません。
この記事では、治らない口内炎や口の乾燥に潜む5つの原因について、医師の視点から徹底解説します。ご自身の症状と照らし合わせ、不安解消の第一歩を踏み出しましょう。
治らない口内炎と乾燥の主な原因5つ
「ただの口内炎だろう」と軽く考えていても、痛みが長引いたり、口の中が乾いて不快だったりすると不安になりますよね。食事や会話もつらくなり、何か悪い病気ではないかと心配になる方も少なくありません。
口内炎は誰にでもできる身近な症状です。しかし、なかなか治らない、あるいは口の乾燥を伴う場合、その背景には注意すべき原因が隠れていることがあります。口の中の環境は非常にデリケートで、全身の健康状態を映し出す「鏡」とも言えます。
ここでは、長引く口内炎と口の乾燥を引き起こす主な5つの原因について、医師の視点から詳しく解説していきます。
ストレスや栄養不足による免疫力の低下
仕事のストレスや慢性的な疲労、睡眠不足が続くと、私たちの体は気づかないうちにダメージを受けています。特に影響を受けやすいのが、体を外部の敵から守る「免疫力」です。
免疫力が低下すると、普段は問題にならない口の中の常在菌のバランスが崩れます。また、粘膜を修復する機能も落ちるため、口内炎ができやすく、治りにくい状態になるのです。
さらに、食生活の乱れも口内炎の大きな原因です。特に、皮膚や粘膜の健康維持に不可欠な栄養素が不足すると、口内炎を繰り返しやすくなります。
【口内炎の予防・改善に関わる主な栄養素】
- ビタミンB2 粘膜の保護や再生に働くため「発育のビタミン」とも呼ばれます。 不足すると口角炎や舌炎も起こしやすくなります。 (多く含まれる食品:レバー、うなぎ、卵、納豆、乳製品)
- ビタミンB6 たんぱく質の代謝を助け、皮膚や粘膜を健康に保つ働きがあります。 (多く含まれる食品:かつお、まぐろ、鶏肉、バナナ)
- ビタミンC 粘膜の強度を高めるコラーゲンの生成を助けます。 また、ストレスへの抵抗力を高める作用も期待できます。 (多く含まれる食品:ピーマン、ブロッコリー、キウイフルーツ)
- 鉄分 粘膜に栄養を運ぶ赤血球の成分です。 不足すると舌がヒリヒリする舌炎を起こすこともあります。 (多く含まれる食品:レバー、赤身肉、あさり、小松菜)
バランスの取れた食事と十分な休息は、粘膜を健康に保ち、口内炎を繰り返さないための基本です。
ドライマウスを引き起こすシェーグレン症候群などの全身疾患
口の中が乾く「ドライマウス(口腔乾燥症)」も、治らない口内炎の重要な原因です。唾液には、口の中を洗い流す自浄作用や、細菌の増殖を抑える抗菌作用、そして粘膜を保護・修復する大切な作用があります。唾液が減るとこれらの働きが弱まり、口内炎ができやすくなるのです。
ドライマウスの原因は様々ですが、特に注意したいのが「シェーグレン症候群」です。これは、免疫システムが誤って自身の唾液腺や涙腺などを攻撃してしまう、慢性的な自己免疫疾患です。近年の研究では、遺伝的な要因や特定の免疫反応が関与していることが分かってきています。
【シェーグレン症候群のセルフチェックリスト】
- 口が乾いて話しにくい、食べ物が飲み込みにくい
- パンやクッキーなどが水分なしで食べられない
- 夜間に喉の渇きで目が覚めることがある
- 目がゴロゴロする、乾いた感じがする
- 虫歯や口内炎が急に増えたと感じる
- 関節の痛みや朝のこわばりがある
このほか、糖尿病や腎臓病なども唾液の分泌を減少させ、ドライマウスや口内炎の原因となることがあります。気になる症状が続く場合は、内科やリウマチ科への相談も検討しましょう。
口腔がんの初期症状やベーチェット病の可能性
ほとんどの口内炎は1〜2週間で自然に治ります。しかし、もし2週間以上経っても治らない、あるいは徐々に大きくなるような場合は、注意が必要です。まれに「口腔がん」の初期症状である可能性があります。
口腔がんは、口の中にできる悪性腫瘍です。初期の段階では痛みがないことも多く、見た目も口内炎と似ているため見過ごされがちです。しかし、進行すると命に関わることもあるため、早期発見が何よりも重要です。
| 一般的な口内炎(アフタ性口内炎) | 注意が必要な口内炎(口腔がんの疑い) | |
| 形 | 円形または楕円形で境界が明瞭 | 形がいびつで、境界がはっきりしない |
| 色 | 中心が白っぽく、周りが赤い | 赤い部分と白い部分が混ざっている |
| 硬さ | 粘膜と同じように柔らかい | 周囲にしこりのような硬さがある |
| 痛み | 触れるとしみるような強い痛み | 痛みが全くない、または持続的な鈍い痛み |
| 治癒期間 | 1〜2週間で自然に治る | 2週間以上治らない、または大きくなる |
| その他 | 歯ぐきなどから出血が続くことがある |
また、口内炎が繰り返しできる病気として「ベーチェット病」も挙げられます。これは口の中だけでなく、皮膚や目、陰部など全身に症状が現れる自己免疫疾患の一種です。ただの口内炎と自己判断せず、上記のような特徴が見られる場合は、口腔外科や耳鼻咽喉科を受診してください。
ウイルスや細菌の感染による口内炎
口の中は常に多くの細菌が存在する環境です。体の免疫力が低下すると、これらの細菌が異常に増殖したり、外部からウイルスが侵入したりして、感染性の口内炎を引き起こすことがあります。
特に、口腔内の湿潤な環境や多様な細菌の存在は、炎症の治りを妨げる一因にもなります。傷口が常に唾液や細菌にさらされるため、皮膚の傷とは治癒の過程が異なるのです。
【主な感染性の口内炎】
- ウイルス性口内炎 単純ヘルペスウイルスの感染が原因のヘルペス性口内炎が代表的です。 唇や口の粘膜に小さな水ぶくれが多数でき、それが破れてびらんや潰瘍になります。 初感染では発熱や強い痛みを伴うことが多いのが特徴です。
- 細菌性口内炎(カタル性口内炎) 入れ歯が合わない、虫歯で歯が欠けているなど、物理的な刺激でできた傷に細菌が感染して起こります。 粘膜が赤く腫れて熱を持ち、口臭が強くなることもあります。
- 真菌性口内炎(カンジダ性口内炎) 口の中に常にいるカンジダというカビ(真菌)が、免疫力の低下などをきっかけに異常増殖して起こります。 頬の内側や舌に、白い苔のような膜が付着し、拭うと赤くただれているのが特徴です。
これらの口内炎は原因となる病原体が異なるため、それぞれに合った治療が必要です。早めに医療機関を受診し、適切な診断を受けることが大切です。
服用中の薬の副作用
現在服用している薬が、口内炎や口の乾燥の原因となっている可能性も考えられます。薬の副作用は、大きく分けて2つのタイプに分けられます。
- 唾液の分泌を抑える副作用 唾液の分泌を減少させる作用を持つ薬は、ドライマウスを引き起こし、結果として口内炎ができやすい環境を作ってしまいます。 (代表的な薬:降圧薬、抗ヒスタミン薬、抗うつ薬など)
- 口の粘膜に直接作用する副作用 薬そのものが口の粘膜細胞の働きを妨げたり、攻撃したりすることで、口内炎を引き起こす場合があります。 (代表的な薬:抗がん剤、免疫抑制剤、一部の抗菌薬など)
もし特定の薬を飲み始めてから口内炎や口の乾燥が気になるようになった場合でも、自己判断で薬をやめることは絶対にしないでください。
まずは、その薬を処方した主治医や、かかりつけの薬剤師に相談することが重要です。「お薬手帳」を持参すると、話がスムーズに進みます。副作用の可能性がある場合、薬の変更や減量、あるいは口内炎に対する適切な治療を検討してもらえます。
症状を和らげる4つのセルフケア方法
「食事のたびにしみて痛い」「口の中が乾いて不快感が続く」など、治らない口内炎と乾燥の症状は本当につらいものです。すぐにでもこの不快感を和らげたいと感じている方も多いでしょう。
病院を受診する前に、ご自身で症状を緩和し、悪化を防ぐためにできることがいくつかあります。特に口の中は、唾液で常に湿っており、無数の細菌が存在し、食事や会話で絶えず動いています。このような特殊な環境は、皮膚の傷とは異なり、薬が留まりにくく治癒を妨げる一因となります。
だからこそ、日々のセルフケアで口内環境を整えることが、症状改善への重要な一歩となるのです。ここでは、今日から始められる4つのセルフケア方法を、医師の視点から具体的にご紹介します。
痛みを抑える市販薬(塗り薬・貼り薬)の選び方
つらい痛みをすぐに和らげたい場合、市販薬の活用が有効です。口内炎の薬には、主に「塗り薬」と「貼り薬」の2種類があります。それぞれの特徴を理解し、症状や口内炎ができた場所に合わせて選ぶことが大切です。
- 塗り薬(軟膏・ゲルタイプ) 指や綿棒で直接患部に塗るタイプです。 複数の口内炎が広範囲にできている場合や、歯茎と唇の間など凹凸があって貼りにくい場所にも使えます。 ただし、唾液で流れやすいという側面もあります。
- 貼り薬(パッチ・フィルムタイプ) 患部に直接貼ることで、薬の成分をしっかり浸透させます。 同時に、食事や歯ブラシなどの物理的な刺激から患部を守ってくれるという大きな利点があります。
薬を選ぶ際は、配合されている成分にも注目しましょう。ご自身の症状に合った成分を選ぶことで、より効果的なケアが期待できます。
| 成分の種類 | 主な働きと成分例 | こんな方におすすめ |
| 抗炎症成分 | 炎症を鎮め、痛みや腫れを抑える (例:トリアムシノロンアセトニド、アズレンスルホン酸ナトリウム) |
患部が赤く腫れてズキズキと痛む方 |
| 殺菌成分 | 細菌の増殖を防ぎ、患部を清潔に保つ (例:セチルピリジニウム塩化物水和物) |
感染を予防し、治癒を早めたい方 |
| 局所麻酔成分 | 患部の感覚を麻痺させ、痛みを直接和らげる (例:リドカイン、アミノ安息香酸エチル) |
食事がつらいなど、とにかく痛みをすぐに抑えたい方 |
市販薬を5〜6日使用しても症状が改善しない、または悪化するような場合は、他の原因も考えられるため、セルフケアを中止して医療機関を受診してください。
口の乾燥を防ぐ保湿ジェルと唾液腺マッサージ
口の中が乾燥すると、唾液による自浄作用や粘膜の保護機能が低下します。これにより、口内炎の痛みが強まったり、治りが遅くなったりします。口の潤いを保つためのセルフケアを積極的に取り入れましょう。
まずは、市販の口腔保湿剤を活用する方法があります。生活スタイルに合わせて使い分けるのがおすすめです。
- ジェルタイプ 保湿効果が長く続きやすいため、特に乾燥が気になる就寝前の使用に適しています。
- スプレータイプ 日中、会話中や会議前など、乾燥を感じたときに手軽に口全体を潤すことができます。持ち運びにも便利です。
- マウスウォッシュタイプ 口腔内を洗浄しながら保湿できます。アルコールは粘膜を刺激し、乾燥を助長することがあるため、アルコールを含まない低刺激性のものを選びましょう。
次に、唾液の分泌そのものを促す「唾液腺マッサージ」も効果的です。リラックスした状態で行いましょう。ただし、マッサージする場所に強い痛みや腫れがある場合は控えてください。
- 耳下腺(じかせん)のマッサージ 耳の前あたり(上の奥歯付近)に指をあて、後ろから前に向かって円を描くように優しくマッサージします。(10回程度)
- 顎下腺(がっかせん)のマッサージ あごの骨の内側の柔らかい部分に指をあて、耳の下からあごの先に向かって数か所を優しく押します。(各5回程度)
- 舌下腺(ぜっかせん)のマッサージ 両手の親指をそろえて、あごの真下の骨の内側部分を舌を押し上げるようにゆっくりと圧迫します。(10回程度)
これらのケアに加えて、こまめな水分補給(カフェインの入っていない水やお茶が望ましい)や、加湿器で室内の湿度を50〜60%に保つことも口の乾燥対策につながります。
食事の工夫と積極的に摂りたい栄養素(ビタミンB群など)
口内炎があると食事が苦痛になり、栄養が偏りがちです。しかし、傷ついた粘膜を修復するためには、バランスの取れた栄養が不可欠です。食事の工夫で痛みを和らげ、回復を助ける栄養素を積極的に摂りましょう。
【食事のポイント】
- 避けるべきもの 香辛料(唐辛子など)、酸味(酢、柑橘類)、塩分の強いものは患部を直接刺激します。 せんべいのような硬いものや、熱すぎる・冷たすぎるものも痛みを増強させるため避けましょう。
- おすすめの調理法 食材は細かく刻んだり、ミキサーにかけたりして、飲み込みやすい形態に工夫します。 「煮る」「蒸す」などの調理法で柔らかくし、温度は人肌程度に冷ますと、しみにくくなります。
【積極的に摂りたい栄養素と多く含む食品】
口の粘膜は新陳代謝が活発なため、その材料となる栄養素を意識して摂ることが大切です。
- ビタミンB2 粘膜の保護・再生に役立ちます。(レバー、うなぎ、卵、納豆)
- ビタミンB6 たんぱく質の代謝を助け、皮膚や粘膜の健康維持をサポートします。(かつお、まぐろ、鶏ささみ、バナナ)
- ビタミンC 粘膜の強度を高めるコラーゲンの生成を助け、ストレスへの抵抗力を高めます。(パプリカ、ブロッコリー、キウイフルーツ)
- 鉄分 不足すると粘膜に栄養が届きにくくなり、弱くなります。(赤身の肉、レバー、あさり、小松菜)
- 亜鉛 細胞の新陳代謝を促し、粘膜の再生を助けます。味覚を正常に保つ働きもあります。(牡蠣、牛肉、チーズ)
痛みが強く食事が難しい場合は、これらの栄養素を含むゼリー飲料や栄養補助食品を一時的に利用するのも一つの方法です。
口腔内を清潔に保つための正しい歯磨きとうがい
口の中に細菌が増殖すると、口内炎の炎症を悪化させたり、治りを遅らせたりする原因になります。痛みがあっても、できる範囲で口腔内を清潔に保つことが非常に重要です。
【歯磨きのポイント】
- 歯ブラシ 毛先が柔らかく、ヘッドが小さいものを選びましょう。患部にブラシが当たらないよう、鏡を見ながら一本一本丁寧に磨くのがコツです。
- 歯磨き粉 発泡剤(ラウリル硫酸ナトリウムなど)や強いミント系の香料が刺激になることがあります。 低刺激性のものを選ぶか、痛みが強い場合は一時的に使用を中止し、水だけで磨くのもよいでしょう。
【うがいのポイント】
歯磨きが難しい場合でも、うがいはこまめに行いましょう。口の中の食べかすや細菌を洗い流し、口内を潤すことで、細菌の増殖を抑える効果が期待できます。
- タイミング 食後や就寝前はもちろん、1日に4回以上を目安に、乾燥が気になったときにも行いましょう。
- うがい液 水やぬるま湯で十分ですが、殺菌成分や抗炎症成分が含まれた刺激の少ない洗口液(マウスウォッシュ)を使うのも効果的です。 ただし、アルコール成分は粘膜を刺激するため、ノンアルコールタイプを選びましょう。
入れ歯を使用している方は、入れ歯自体が細菌の温床にならないよう、清潔に保つことが大切です。毎食後にすすぎ、1日1回は専用のブラシと洗浄剤で丁寧に洗浄しましょう。正しい口腔ケアは、口内炎の早期回復と再発予防の基本となります。
病院を受診する目安と専門的な治療法
市販薬を試したり、セルフケアを工夫したりしても口内炎が良くならないと、「何か悪い病気ではないか」という不安が大きくなりますよね。ほとんどの口内炎は自然に治りますが、中には専門的な治療を必要とするケースも隠れています。
大切なのは、ご自身の症状を正しく見極め、適切なタイミングで専門家の助けを求めることです。セルフケアで改善しない場合は、一人で抱え込まずに医療機関を受診しましょう。ここでは、病院へ行くべきタイミングや、どのような検査・治療が行われるのかを具体的に解説します。
2週間以上治らない場合は受診を!危険な症状の見分け方
口の中の粘膜は、皮膚と同じように新陳代謝(ターンオーバー)を繰り返しており、通常であれば1〜2週間で新しい細胞に生まれ変わります。そのため、一般的な口内炎はこの期間内に自然治癒することがほとんどです。
このことから、「2週間」というのが、病院を受診すべきか判断するための一つの重要な目安になります。もし2週間以上経っても改善しない、あるいは悪化している場合は、単なる口内炎ではない可能性を考える必要があります。特に、以下のような症状が見られる場合は、早めに医療機関に相談してください。
【受診を強く推奨する症状のチェックリスト】
- 治癒期間 口内炎が2週間以上経っても治らない、または徐々に大きくなっている。
- 痛み 痛みがどんどん強くなり、食事や水分補給、会話が困難になっている。
- 形状と硬さ 患部の境目がはっきりせず、周りの粘膜にしこりのような硬さを感じる。
- 出血 歯磨きなどの軽い刺激がないのに、何度も出血を繰り返す。
- 数と場所 口内炎が1つだけでなく、次々と複数個できたり、広範囲に広がったりする。 一度治っても、すぐに同じような場所に再発を繰り返す。
- 全身症状 発熱や全身の倦怠感、関節の痛み、皮膚の発疹などを伴う。
これらの症状は、ベーチェット病のような全身性の病気や、まれに口腔がんの初期症状である可能性も否定できません。不安な症状があれば、自己判断で様子を見続けず、専門医の診察を受けることが早期発見・早期治療につながります。
何科を受診すべき?歯科・口腔外科・耳鼻咽喉科の選び分け
口内炎で病院に行こうと思ったとき、どの診療科を選べばよいか迷うかもしれません。口の中のトラブルは、主に歯科、口腔外科、耳鼻咽喉科で診療しています。それぞれの科の特徴を知り、ご自身の症状に合わせて選ぶのがよいでしょう。
| 診療科 | こんなときにおすすめ | 特徴 |
| 歯科・口腔外科 | ・一般的な口内炎 ・歯や入れ歯が当たって痛い ・歯茎や舌、頬の内側の症状 ・口腔がんが心配な場合 |
口の中全体の専門家です。特に口腔外科は、口内炎の診断から、必要に応じて組織検査やレーザー治療などの外科的処置まで幅広く対応できます。まずは口の中のトラブル全般を相談できる窓口です。 |
| 耳鼻咽喉科 | ・喉の奥や扁桃腺、舌の付け根の症状 ・飲み込みにくさや声のかすれを伴う場合 ・鼻や喉にも不調がある場合 |
口の中から喉にかけての広範囲を診る専門家です。ファイバースコープなどの器具を使い、ご自身では見えにくい口の奥にできた口内炎の診察に適しています。 |
| 内科・リウマチ科 | ・口の乾燥や目の乾きを強く感じる ・皮膚の発疹や関節痛など全身症状がある ・原因が分からず繰り返し口内炎ができる |
口内炎が全身の病気の一症状として現れている可能性を考えます。例えば、シェーグレン症候群は口や目の強い乾燥が特徴の自己免疫疾患で、リウマチ科が専門です。この病気は全身に影響を及ぼし、悪性リンパ腫のリスクを高める可能性も指摘されており、専門的な精査が重要になります。 |
どの科を受診すればよいか迷う場合は、まずはかかりつけの歯科医や内科医に相談し、症状に応じて適切な専門医を紹介してもらうのも一つの確実な方法です。
病院で行われる検査(視診・血液検査・組織検査)
病院では、口内炎の原因を正確に突き止めるために、いくつかの検査を行います。もちろん、すべての検査を行うわけではなく、医師が症状を診て必要と判断した場合に実施されます。
- 問診・視診 最初に、いつからどのような症状があるか、生活習慣、服用中の薬などについて詳しくお話を伺います。その後、医師が直接お口の中をライトで照らし、口内炎の大きさ、形、色、硬さ、場所などを丁寧に観察します。多くの場合、この視診である程度の診断がつきます。
- 血液検査 栄養状態の偏り(ビタミンや鉄分の不足)や、ウイルス感染などが疑われる場合に行います。また、口内炎を繰り返す背景に全身の病気が隠れていないか調べる目的もあります。特に、シェーグレン症候群のような自己免疫疾患が疑われる場合は、自己抗体(自分の体を誤って攻撃してしまうタンパク質)の有無などを調べるために、血液検査が非常に重要な情報となります。
- 組織検査(生検) 視診で悪性の病気(口腔がんなど)の可能性が少しでもあると判断された場合に行われる、確定診断のための検査です。患部にごく少量の局所麻酔をした後、組織の一部(米粒程度)を採取し、顕微鏡で細胞の種類や状態を詳しく調べます。これにより、良性か悪性かを正確に判断できます。
専門的な治療(レーザー治療・ステロイド薬・漢方薬)
セルフケアや市販薬では対応が難しい口内炎に対し、医療機関ではより専門的な治療を行います。原因や症状の程度に合わせて、以下のような治療法が選択されます。
- レーザー治療 痛みが強く、食事に支障が出ている口内炎に対して行われることがあります。患部にレーザーを照射すると、表面に薄い膜が作られます。これがバリアとなり、食べ物などの物理的な刺激を遮断して痛みを大幅に和らげます。また、血行を促進し、治癒を早める効果も期待できます。
- 薬物療法(ステロイド薬など) 炎症を抑える作用が強いステロイド成分を含んだ軟膏や貼り薬が処方されます。市販薬よりも高い効果が期待できますが、ウイルス性などの感染性の口内炎に使うと症状を悪化させることもあるため、必ず医師の診断のもとで使用します。症状が広範囲な場合や、全身疾患が原因の場合は、飲み薬が処方されることもあります。
- 漢方薬 体質から改善し、口内炎を繰り返しにくい身体づくりを目指す場合に用いられます。体の熱や炎症を冷ますもの(黄連解毒湯など)、粘膜を潤すもの(麦門冬湯など)、免疫力を高めるもの(補中益気湯など)を、一人ひとりの体質や症状に合わせて処方します。
- 原因疾患の治療 シェーグレン症候群のような全身疾患が原因の場合は、口内炎への対症療法と並行して、病気そのものに対する治療が不可欠です。病気の根本にある免疫の異常に働きかけるバイオ医薬品や低分子化合物など、腺機能の回復や全身の症状軽減を目指した治療法の研究開発が進められています。原因を根本から治療することが、結果的に口内炎の再発予防につながるのです。
まとめ
今回は、なかなか治らない口内炎の原因から、ご自身でできるセルフケア、病院での専門的な治療法まで詳しくご紹介しました。
口内炎は誰にでもできる身近な症状ですが、長引く痛みはつらいものです。その原因はストレスや栄養不足だけでなく、時にはシェーグレン症候群や口腔がんといった病気のサインである可能性も隠れています。
まずは生活習慣を見直し、市販薬などでケアを試すことも大切ですが、「2週間以上治らない」「しこりがある」など、少しでも不安な症状があれば、決して一人で抱え込まないでください。「たかが口内炎」と軽視せず、早めに歯科・口腔外科など専門医に相談することが、ご自身の安心と健康につながります。
参考文献
- Zhang X, Lei J, Qu T and Zhang X. “Advances in chitosan-based materials for oral ulcer treatment.” Carbohydrate polymers 368, no. Pt 1 (2025): 124110.
- Wang D, Liu Y, Lu X and Xu F. “Advanced strategies for targeting molecular pathways in Sjögren’s syndrome.” Biochemical pharmacology 241, no. (2025): 117116.
追加情報
[title]: Advances in chitosan-based materials for oral ulcer treatment.
キトサンベース材料による口腔潰瘍治療の進歩 【要約】
- 口腔潰瘍は世界中で広くみられる疾患であり、強い痛みと不快感を引き起こす。
- 口腔内の湿潤環境や動的な性質、多様な口腔内細菌叢は、従来の口腔潰瘍治療法にとって課題となっている。
- キトサンは口腔潰瘍治療における有望な治療薬として注目されている。
- 本レビューは、2000年から2025年に行われた査読済み論文34報を統合的に検討し、キトサンベース製剤(ハイドロゲル、マイクロニードル、ナノ粒子担体、口腔フィルム、ナノファイバー足場など)に焦点を当てている。
- これらのキトサンベース材料は、従来の治療法と比較して高い有効性を示すことが示唆された。
- しかし、一時的な付着性、共生細菌叢を破壊する可能性のある非選択的な抗菌活性、唾液によるせん断力下での機械的不安定性といった限界も残されている。
- 材料科学と精密製造技術の統合により、次世代のキトサンプラットフォームが開発される可能性がある。
- 本レビューは、口腔潰瘍の特徴、キトサンの生物活性、様々なキトサンベース材料について解説し、新たなキトサンベース治療戦略の開発と応用を支援する貴重な知見を研究者と臨床医に提供することを目的としている。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40912776
[quote_source]: Zhang X, Lei J, Qu T and Zhang X. “Advances in chitosan-based materials for oral ulcer treatment.” Carbohydrate polymers 368, no. Pt 1 (2025): 124110.
[title]: Advanced strategies for targeting molecular pathways in Sjögren’s syndrome.
【要約】
- シェーグレン症候群(SS)は、非常に攻撃的で慢性的な性質を持つ、リウマチ性疾患の中でも独特な疾患であり、主に外分泌腺に影響を与え、口渇やドライアイなどの症状を引き起こす。
- しかし、その影響は分泌不全にとどまらず、他の臓器系にも影響を及ぼし、非ホジキンB細胞リンパ腫の可能性を高める。
- 近年の研究により、遺伝的脆弱性、唾液腺における拡張免疫反応、そして1型インフルエンザ経路の役割が明らかになり、その病態生理学的理解が深まっている。
- SSの病態生理を標的とする新たなバイオ医薬品や低分子化合物が、医薬品開発パイプラインで進歩している。
- 本レビューは、腺機能の回復と全身的な疾患負担の軽減を目指した新たな治療戦略、そして原発性シェーグレン症候群の病因に関する最近の進歩に焦点を当てている。
- 本研究は文献の批判的レビューを通じて、SSにおける免疫異常の中心的な役割を強調し、バイオ医薬品や標的分子介入を含む新たな治療戦略を探求している。
- 統合的な治療アプローチを提唱し、臨床研究において腺以外の症状に対処する必要性を強調している。
- 本レビューは、SSの病態発生に関するより深い理解に貢献し、将来の治療的進歩の基礎を提供する。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40619026
[quote_source]: Wang D, Liu Y, Lu X and Xu F. “Advanced strategies for targeting molecular pathways in Sjögren’s syndrome.” Biochemical pharmacology 241, no. (2025): 117116.
監修者情報
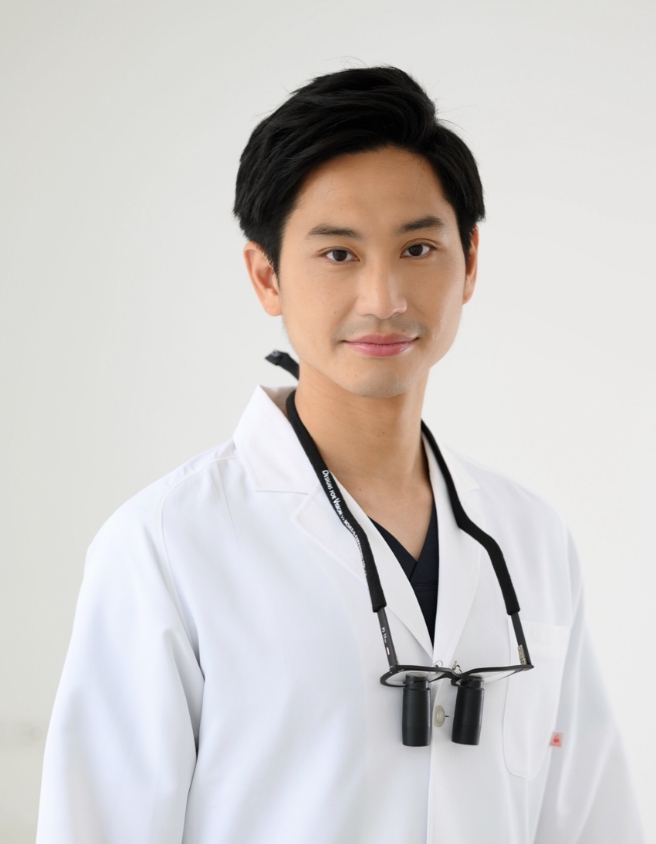
牧野歯科・矯正歯科 歯科医師
牧野 盛太郎Seitaro Makino
略歴
所属学会
- 日本口腔外科学会認定医
- 日本再生医療学会認定医
- 日本口腔外科学会
- 日本再生医療学会
- 日本顎顔面インプラント学会
- 日本口腔インプラント学会