ブログ
ダイレクトボンディングによる虫歯治療
「虫歯治療は歯を大きく削るもの」「銀歯が目立つのは仕方ない」そんな常識は、もう過去のものかもしれません。虫歯も部分だけを取り除き、1回の通院で治療が完了する場合も多く、天然の歯に近い自然な見た目に修復を目指す「ダイレクトボンディング」という治療法があります。
この記事では、健康な歯をできるだけ残すことを目指すこの治療法の5つの特徴を、専門家の視点から解説します。金属アレルギーの心配がなく、審美性にも優れた選択肢について、費用や他の治療法との違いも交えながら、あなたの歯の未来を変えるかもしれない大切な情報をお届けします。
歯を削らない治療 ダイレクトボンディングの5つの特徴
虫歯に侵された部分だけを精密に取り除き、「コンポジットレジン」という歯科用の高機能プラスチックを直接歯に盛り付け、光を当てて固めることで修復します。
歯を削る量を最小限に抑え、ご自身の天然歯に近い自然な見た目を再現できるのが大きな特徴です。これから、ダイレクトボンディングが持つ5つの特徴について、歯科医師の視点から一つひとつ詳しく解説していきます。

健康な歯をできるだけ多く残すことを目指す低侵襲な治療法
ダイレクトボンディングは、「MI治療(Minimal Intervention:最小限の侵襲)」という現代歯科治療の基本理念に基づいた、歯に優しい低侵襲な治療法です。MI治療とは歯をできるだけ削らず、生まれ持った歯の組織を最大限に残すことを最優先する考え方です。
従来の保険適用の虫歯治療、特に銀歯などの詰め物(インレー)を入れる場合を考えてみましょう。この場合、虫歯の部分を削るだけでは不十分でした。詰め物が外れたり、壊れたりしないように、箱のような特定の形(維持形態)に窩洞を整える必要があり、健康な歯の部分も大きく削らざるを得なかったのです。
しかし、ダイレクトボンディングでは歯科用接着剤の進化により、コンポジットレジンという材料を歯に直接、強力に接着させることが可能です。そのため、維持形態を作るための追加的な切削が不要となり、虫歯に侵された部分のみを選択的に、精密に除去するだけで治療ができます。
歯は一度削ってしまうと、再生することはありません。健康な歯質を少しでも多く残すことは、歯そのものの強度を維持し、将来的な破折のリスクを減らし、歯そのものの強度を維持し、将来的な破折のリスクを減らすことで、歯を長持ちさせることを目指します。ご自身の歯を生涯大切にしたいと考える方にとって、ダイレクトボンディングは非常に合理的な治療法といえるでしょう。
天然歯に近い白さと透明感で見た目が自然
ダイレクトボンディングの大きな魅力の一つは、天然歯に近く、自然な仕上がりを目指せる高い審美性です。治療に用いるコンポジットレジンには、患者さん一人ひとりの歯の色に合わせられるよう、非常に多くの色調(シェード)が用意されています。
歯科医師は、治療する歯だけでなく、隣接する歯の色や透明度を注意深く観察し、最も調和する色のレジンを選択します。しかし、ただ一色のレジンを詰めるだけでは、本当に自然な見た目にはなりません。
天然の歯は、内側にあって歯の色を決定づける「象牙質」と、その外側を覆う半透明の「エナメル質」の二層構造でできています。この複雑な構造を再現するため、「積層充填」という高度なテクニックを用います。これは、色の濃さや透明感が異なる複数のレジンを、絵の具を重ねるように一層ずつ丁寧に盛り付けていく方法です。
この積層充填により、天然歯が本来持っている特有の透明感や色のグラデーション、表面の微細な凹凸まで忠実に再現します。その結果、周囲の歯と自然に馴染ませることを目指します。特に人目に付きやすい前歯の治療や、笑顔になった時に見える部分の虫歯治療において、その審美性の高さは大きな利点となります。
1回の通院で完了できる場合が多い
お仕事や学業、あるいは育児などで多忙な日々を送る方にとって、何度も歯科医院に通院する時間を確保するのは難しいことです。ダイレクトボンディングは、多くのケースで1回の通院で治療が完了するため、時間的な負担を大幅に軽減できるというメリットがあります。
詰め物(インレー)や被せ物(クラウン)による従来の治療では、一般的に以下のような手順を踏むため、最低でも2回の通院が必要でした。
- 1回目の通院 虫歯を削り、精密な歯の型取りを行う。
- 歯科技工所での作製 模型を元に、技工所で詰め物・被せ物を作製する(約1〜2週間)。
- 2回目の通院 後日、完成した技工物を歯に装着する。
一方、ダイレクトボンディングは、虫歯を削ったその日のうちに、歯科医師が直接お口の中でコンポジットレジンを充填し、形を整えて硬化させるまでの一連の作業を行います。歯の型取りや歯科技工所での作製工程が一切不要なため、即日修復が可能なのです。
治療時間は、虫歯の大きさや部位、修復の複雑さにもよりますが、1本の歯につき概ね30分から90分程度が目安となります。治療期間の短縮は、患者さんの身体的な負担を減らすことにも繋がります。
銀歯やインレーなど他の詰め物との違い
虫歯治療で用いられる詰め物には、ダイレクトボンディング以外にも様々な選択肢があります。それぞれの特徴を正しく理解し、ご自身の希望や歯の状態に最も合った治療法を選ぶことが重要です。
- 銀歯(メタルインレー) 保険が適用されるため安価ですが、審美性に劣り、金属アレルギーのリスクがあります。また、歯と金属では熱による膨張率が異なるため、長年の使用で隙間が生じやすく、そこから細菌が侵入して歯と金属の境目に隙間が生じ、二次虫歯のリスクに注意が必要な場合があります。
- セラミックインレー 審美性と耐久性に優れ、生体親和性も高くアレルギーの心配もありません。しかし、ダイレクトボンディングと同様に自費診療であり、技工物として装着するためには、ある程度健康な歯を削る必要があります。
ダイレクトボンディングは、歯を削る量を抑えつつ審美性を確保できる点や、1回で治療が終わる場合がある点などが特徴です。
金属アレルギーの心配がないセラミック粒子配合の素材
ダイレクトボンディングで使用するコンポジットレジンは、主にセラミックの微粒子と合成樹脂を混ぜ合わせたハイブリッド材料です。金属を一切含まないメタルフリー素材のため、金属アレルギーをお持ちの方や、その心配がある方でも治療の選択肢となります。また、金属イオンが溶け出して歯ぐきを黒ずませる「メタルタトゥー」の心配もありません。
ダイレクトボンディングの治療費用と流れ
「歯を削らない治療は魅力的だけど、費用はいくら?」「実際の治療はどんな手順で進むの?」このような疑問は、ダイレクトボンディングを検討する上で誰もが抱くものです。
歯の健康と美しさを両立することを目指す治療法ですが、安心して治療に臨むためには、費用や具体的な流れを事前に把握しておくことが欠かせません。
ここでは、カウンセリングから治療完了までのステップ、保険診療との違い、痛みへの配慮など、患者さんが知りたい情報を歯科医師の視点から詳しく解説します。
カウンセリングから治療完了までの具体的なステップ
ダイレクトボンディングは、歯科医師の技術と経験が仕上がりを大きく左右する、非常に繊細な治療です。多くの場合、1回の通院で完了しますが、その裏側には精密なステップが存在します。
- カウンセリング・診査診断 まず、患者さんのお悩みや理想の仕上がりについて詳しく伺います。その上で、レントゲン撮影や口腔内カメラ、場合によっては歯科用CTを用いて、虫歯の深さや範囲、歯の神経との距離を三次元的に正確に診断します。ダイレクトボンディングが本当に適した治療法かを見極める、非常に重要な工程です。
- 歯のクリーニング・色の確認 より良い治療効果を得るため、まず歯の表面を専門の器具で清掃します。その後、シェードガイドと呼ばれる色見本を使い、患者さんご自身の歯の色を精密に分析します。天然歯は均一な色ではないため、透明感や色の濃淡が異なる複数のレジンを組み合わせ、自然なグラデーションを再現する計画を立てます。
- 虫歯部分の除去と感染対策 治療中の唾液の侵入を防ぎ、清潔な環境を確保するために「ラバーダム防湿」というゴムのシートでお口を保護することがあります。う蝕検知液で虫歯菌に侵された部分だけを染色し、拡大鏡やマイクロスコープで視野を拡大しながら、健康な歯質をミリ単位で残すよう慎重に削り取ります。
- 接着処理(ボンディング) 歯とコンポジットレジンを強力に一体化させるための、治療における重要な工程です。歯の表面に特殊な薬剤を塗布し、接着力を高める下準備をします。この工程を丁寧に行うことで、治療後の脱離や二次虫歯のリスクを低減することを目指します。
- コンポジットレジンの充填・積層 ペースト状のコンポジットレジンを、歯に直接盛り付けていきます。天然歯の構造(象牙質とエナメル質)を再現するため、色の異なるレジンを何層にも重ねて詰める「積層充填」という高度な技術を用います。これにより、本物の歯のような奥行きと透明感が生まれます。
- 形の調整と研磨 特殊な光を照射してレジンを完全に硬化させた後、噛み合わせや周囲の歯との調和を確認しながら、解剖学的に自然な形に整えます。最後に、表面を様々な研磨器具で段階的に磨き上げ、プラークが付着しにくい滑沢な状態に仕上げて治療完了です。
保険適用と自費診療の費用の違いと相場
ダイレクトボンディングは、審美性や精密性、そして長期的な安定性を追求する治療のため、原則として保険適用外の自費診療となります。
【費用の相場】
費用は、治療する歯の部位や虫歯の大きさ、修復の難易度によって変動します。
- 1歯あたり 33,000円~66,000円(税込)
保険診療に比べ費用は高額になります。ダイレクトボンディングは歯を削る量を抑え、天然歯に近い色調に仕上げられるといった特徴があります。なお、自費診療は医療費控除の対象となり、確定申告で税金の還付を受けられる場合があります。
治療中の痛みと麻酔の必要性について
「歯の治療=痛い」というご不安をお持ちの方もダイレクトボンディングは、痛みを伴いにくいとされる治療法の一つです。
【痛みが少ない理由】
歯の最も外側にあるエナメル質には神経が通っていません。ダイレクトボンディングは、このエナメル質や、その内側にある象牙質の浅い層までの虫歯を対象とすることが多く、神経への刺激を最小限に抑えられるためです。
【麻酔の必要性】
- 多くの場合、麻酔は不要です: ごく初期の小さな虫歯であれば、麻酔注射なしで治療が可能です。
- 麻酔を使用するケース:
- 虫歯が象牙質の深い部分まで進行している場合
- もともと歯がしみやすい(知覚過敏)方
- 治療に対する不安や恐怖心が特に強い方
麻酔が必要な場合でも、注射の痛みを軽減するために、事前に歯ぐきに表面麻酔のジェルを塗ったり、極細の注射針や電動麻酔器を使用したりと、痛みを軽減するための配慮をしています。
虫歯の大きさや場所による適応・非適応ケース
ダイレクトボンディングは万能な治療法ではなく、お口の状態によっては他の治療法が適している場合があります。
【ダイレクトボンディングが適しているケース】
- 初期~中程度の比較的小さな虫歯
- 審美性が求められる前歯や小臼歯の虫歯
- 古い金属の詰め物を白く自然にやり替えたい場合
- 金属アレルギーがあり、メタルフリー治療を希望する場合
【他の治療法を検討すべきケース】
- 虫歯が神経に達している、または歯の大部分を失っている場合 失った部分が大きすぎると、レジンだけでは強度を確保できません。この場合は、歯全体を覆うセラミックの被せ物(クラウン)などが適応となります。
- 歯ぎしりや食いしばりの癖が強い方の奥歯 奥歯には食事の際に非常に強い力がかかります。過度な負担でレジンが破損するリスクがあるため、より強度の高いセラミックインレーやジルコニアインレー(詰め物)が推奨されることがあります。
- 歯ぐきの下深くまで虫歯が進行している場合 治療部位を完全に乾燥させることが難しく、レジンの接着力が著しく低下するため、適応外となることがあります。
どの治療法が最適かは、歯科医師が診査を行い総合的に判断します。
前歯の隙間や欠けた歯の修復も可能
ダイレクトボンディングは虫歯治療だけでなく、審美的なお悩みを改善するための一つの選択肢となります。歯をほとんど削らずに、気になる部分の形や色を美しく整えることができます。
【審美修復の具体例】
- すきっ歯(正中離開)の改善: 前歯の隙間をレジンで埋め、自然な歯並びに見せます。
- 欠けた歯の修復: 事故などで欠けてしまった歯の形を、元の状態に回復させます。
- 歯の形の修正: 生まれつき小さい歯(矮小歯)の大きさを整え、全体のバランスを改善します。
さらに、ダイレクトボンディングで用いる材料は、単に形を整えるだけでなく、科学的にも進化を続けています。近年の研究では、コンポジットレジンに抗菌作用を持つ金属系のナノ粒子などを応用する試みが進んでいます。
これにより、材料自体が虫歯の原因菌の活動を抑制する効果が期待されています。ダイレクトボンディングは、審美的な改善を目指す治療法の一つです。
治療後の歯を長持ちさせるための重要なポイント
ダイレクトボンディングは、歯を削る量を抑え、自然な見た目に回復を目指せる治療法です。
せっかく時間と費用をかけて治療した歯ですから、できるだけ長く、良い状態を保ちたいと誰もが願うことでしょう。
治療後の歯の寿命は、術者の技術力はもちろんのこと、その後の「患者さんご自身のケア」と「歯科医院でのプロフェッショナルなケア」という二つの車の両輪によって大きく左右されます。
ここでは、ダイレクトボンディングで治療した歯を長持ちさせるために特に重要な4つのポイントについて、歯科医師の視点から詳しく解説していきます。

ダイレクトボンディングの平均的な寿命
ダイレクトボンディングの寿命を「何年です」と断言することは困難です。なぜなら、治療後の歯がどのくらい持つかは、患者さん一人ひとりの口腔環境や生活習慣に大きく依存するためです。
治療後の歯がどのくらい持つかは、患者さん一人ひとりの口腔環境や生活習慣に大きく依存します。適切なケアとメンテナンス次第で、これを大幅に超えて長持ちさせることも十分に可能です。
寿命に影響を与える主な要因は以下の通りです。
- 噛む力や癖 硬いものを好む習慣や、睡眠中の歯ぎしり・日中の食いしばり癖があると、修復物に想定外の強い力がかかります。これにより、微細な亀裂や欠け、最悪の場合は脱離につながるリスクが高まります。
- セルフケアの質 毎日の歯磨きで、治療した部分とご自身の歯との「境目」をいかに丁寧に清掃できているかが、二次虫歯を防ぐ上で極めて重要です。
- 定期メンテナンスの有無 セルフケアだけでは除去しきれない汚れの蓄積や、ご自身では気づけない微細な変化を早期に発見・対処できるかで、寿命は大きく変わります。
| 寿命を延ばすためのポイント | 具体的なアクション |
|---|---|
| 過度な力を避ける | 氷やナッツの殻、硬い飴などを直接噛まないように注意する。 |
| 歯ぎしり・食いしばり対策 | 自覚がある場合や歯科医師に指摘された場合は、就寝時に専用のマウスピース(ナイトガード)を装着して歯を保護する。 |
| 丁寧なセルフケア | 修復物と歯の境目を意識し、毛先の柔らかい歯ブラシで優しく磨く。歯間ブラシやデンタルフロスを毎日使用し、歯と歯の間の汚れを確実に除去する。 |
| プロによるケアの継続 | 歯科医院での定期メンテナンスを3~6ヶ月に一度は必ず受診する。 |
変色や着色を防ぐための食事や生活での注意点
ダイレクトボンディングで用いるコンポジットレジンは、天然歯に近い色調を再現できますが、材料の特性上、わずかに水分を吸収します。そのため、色の濃い飲食物による着色(ステイン)が起こりやすい側面があります。
特に、治療後24時間以内はレジンが硬化する過程にあるため、着色しやすい状態です。この期間は、色の濃い飲食物は避けるようにしましょう。
【着色しやすい飲食物の例】
- 飲み物 コーヒー、紅茶、赤ワイン、ウーロン茶、コーラ、色の濃い野菜ジュースなど
- 食べ物 カレー、ミートソース、ケチャップ、醤油、ソース、チョコレート、ベリー類など
- その他 タバコのヤニ、一部のうがい薬(クロルヘキシジン配合のものなど)
これらの飲食物を完全に断つ必要はありません。摂取した後は、できるだけ早く水で口をすすいだり、歯を磨いたりする習慣が大切です。また、飲み物の場合はストローを使い、液体が前歯に直接触れるのを防ぐことも着色予防に効果的です。
喫煙は、歯の着色の主な原因の一つです。タバコのヤニは粘着性が高く、歯磨きだけでは落とせません。さらに、ニコチンは歯肉の血流を悪化させ、歯周病のリスクを高めます。ダイレクトボンディングの美しさと口腔全体の健康のために、禁煙を強くお勧めします。
虫歯の再発を防ぐ定期メンテナンスの重要性
治療した歯を長持ちさせる上で、歯科医院での定期メンテナンスも重要です。
ダイレクトボンディングで修復した部分とご自身の歯との境目は、どんなに精密に治療しても、ミクロの視点では構造上の段差が存在します。ここはプラーク(細菌の塊)が溜まりやすい弱点となり、ここから虫歯が再発する「二次カリエス」は、詰め物がダメになる主な原因の一つです。
定期メンテナンスでは、以下のような専門的なケアで二次カリエスのリスクを低減させます。
- 専門家によるクリーニング(PMTC) 専用の機器とペーストを使い、ご自身の歯磨きでは落としきれないプラークや着色を除去します。
- 修復物の状態チェック マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)などを使い、修復物に欠けや摩耗がないか、歯との境目に微細な隙間ができていないかを精密に確認します。
- 表面の再研磨(ポリッシング) 修復物の表面を滑沢に磨き直すことで、汚れや着色の再付着を防ぎ、プラークが溜まりにくい状態を維持します。
- 噛み合わせの調整 日々の生活で噛み合わせは微妙に変化します。修復物に過度な負担がかかっていないかを確認し、必要であれば微調整を行います。
術者の技術力で変わる仕上がりと歯科医院の選び方
ダイレクトボンディングは、歯科医師がお口の中で直接、歯の形をゼロから作り上げていく、歯科医師がお口の中で直接、歯の形態を精密に作り上げていく側面を持つ治療法です。そのため、歯科医師の技術力、経験、そして美的センスが治療結果に直接反映される「術者依存性」が高い治療といえます。
技術力の差は、以下のような点に現れます。
- 審美性 天然歯が持つ複雑な色合いや透明感、蛍光性といった光学的特性を、何種類ものレジンを重ねて(積層充填)、いかに忠実に再現できるか。
- 接着精度 唾液などによる湿気を可能な限り防ぐ「ラバーダム防湿」などを行い、歯とレジンを緊密に接着させる技術。この精度が低いと、早期の脱離や二次カリエスの原因となります。
- 形態再現性 本来の歯が持つ機能的な凹凸や丸みを解剖学的に正確に再現し、清掃しやすい滑らかな形態に仕上げる技術。
満足のいくダイレクトボンディング治療を受けるには、信頼できる歯科医院を慎重に選ぶことが重要です。
【歯科医院選びのチェックリスト】
- ウェブサイトなどで、治療に関する詳しい情報や考え方を公開しているか
- 治療のメリットだけでなく、デメリットやリスク、他の治療選択肢についても丁寧に説明してくれるか
- マイクロスコープやルーペ(拡大鏡)を使用し、精密な治療を行っているか
- 精密な治療には相応の時間がかかるため、治療にどのくらいの時間をかけているかを確認することも参考になります。
まとめ
今回は、歯を削る量を最小限に抑え、白く美しい見た目を目指すダイレクトボンディング治療について、その特徴から費用、長持ちさせる秘訣まで詳しくご紹介しました。
この治療法は、ご自身の歯を大切にしながら、機能性と審美性を両立できる選択肢の一つです。しかし、その効果を最大限に引き出すには、歯科医師の精密な技術と、治療後の丁寧なセルフケアや定期メンテナンスが欠かせません。
「銀歯が気になる」「できるだけ歯を削りたくない」といったお悩みをお持ちでしたら、ダイレクトボンディングがあなたの希望を叶えるかもしれません。まずは信頼できる歯科医師へ気軽に相談し、ご自身の歯にとって最適な治療法を一緒に見つけていきましょう。
追加情報
[title]: Modulating the oral microbiome with dental biomaterials: A review of challenges, advances, and future perspectives.
歯科用バイオマテリアルを用いた口腔マイクロバイオームの調節:課題、進歩、そして将来展望 【要約】
- 口腔マイクロバイオームは、口腔および全身の健康維持に重要な役割を果たしている。
- 近年の研究では、歯科用バイオマテリアルが複雑な口腔内細菌叢を調節する可能性が示されている。
- 口腔環境のダイナミックさによる短い滞留時間を考慮した、独自の設計が必要となる。
- 本レビューでは、プロバイオティクス送達プラットフォーム、幹細胞移植、金属イオン放出ハイドロゲル、抗菌・抗酸化物質、エナメル質模倣膜など、口腔マイクロバイオームを調節するバイオマテリアルの最近の進歩について概説している。
- これらの歯科用バイオマテリアルは、Porphyromonas gingivalisなどの病原菌を選択的に抑制し、共生菌を促進する。
- バイオミメティクス設計と人工知能支援による材料開発は、有望な戦略として台頭している。
- 最終的に、口腔マイクロバイオームを調節する歯科用バイオマテリアルは、有益な共生菌の唾液を介した移行を促進することにより、腫瘍や心血管疾患などの全身疾患の治療に活用できる可能性がある。
- 個別化された口腔マイクロバイオームの調節と臨床応用への成功には、微生物学と材料科学の統合が不可欠である。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40815896
[quote_source]: Choi W and Hong J. “Modulating the oral microbiome with dental biomaterials: A review of challenges, advances, and future perspectives.” Biomaterials 325, no. (2026): 123610.
[title]: Mechanistic insights and therapeutic applications of metal-based nanomaterials in oral infectious diseases: Current advances and future perspectives.
金属系ナノ材料による口腔感染症治療:メカニズムと臨床応用 【要約】
- 口腔感染症(う蝕、歯髄炎、歯周炎、インプラント周囲炎、顎骨骨髄炎など)は、細菌感染が主な原因で、非常に頻度の高い疾患である。
- 従来の治療法(機械的デブリードマン、抗菌薬療法)は、耐性菌の出現、不十分な感染制御、組織再生促進能力の不足といった限界がある。
- 金属系ナノ材料は、広範囲の抗菌作用、免疫調節作用、再生促進作用を示すため、これらの課題解決に有効な手段として期待されている。
- 本論文は、金属系ナノ材料の抗菌メカニズム(細胞膜破壊、酸化ストレス誘導、代謝干渉など)と、炎症調節、組織再生促進(幹細胞分化、細胞外マトリックスリモデリングなど)における役割を詳細に分析している。
- う蝕予防、歯内療法、歯周治療、インプラント治療におけるこれらのナノ材料の応用についても検証している。
- バイオセーフティ、臨床応用における課題、材料最適化戦略についても言及している。
- 本レビューは、最近の進歩と今後のトレンドをまとめることで、革新的なナノ治療薬の開発による口腔医療の向上への洞察を提供することを目的としている。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40587916
[quote_source]: Wu Y, Liao J, Pu Y, Gong L, Liu X, Wu Y, Zhang Q, Gu F, Wang Y and Lin Z. “Mechanistic insights and therapeutic applications of metal-based nanomaterials in oral infectious diseases: Current advances and future perspectives.” Biomaterials 324, no. (2026): 123528.
[title]: Soft tissue integration around dental implants: A pressing priority.
歯周組織インプラント周囲の軟組織統合:喫緊の課題 【要約】
- 歯槽骨との結合(オッセオインテグレーション)に加え、長期的なインプラント成功には、強靭で生物学的に統合された軟組織シール(歯肉など)の形成が非常に重要であることが、最近の研究で強調されている。
- 本論文では、インプラント周囲の軟組織統合を促進するための分子、細胞、材料科学戦略に関する最近の進歩(主に過去5年間)を批判的に検討している。
- 重要な要素として、マイクロおよびナノスケールレベルでの精密に設計された表面構造、濡れ性とタンパク質吸着を向上させる表面化学修飾、細胞外マトリックス由来ペプチド、ケモカイン、成長因子を含む生体模倣コーティングが挙げられる。
- レーザーマイクロ・ナノテクスチャリング、プラズマ処理、生体機能化による線維芽細胞と上皮細胞の挙動調節、組織付着の促進、初期炎症反応の軽減に関する最近の研究結果が示されている。
- プラットフォームスイッチングや粘膜透過性ジルコニアアバットメントなどの新しいインプラント・アバットメント設計は、軟組織の安定性を向上させ、骨頂部骨吸収を軽減する。
- 次世代材料の免疫調節の可能性は、マクロファージの分極を制御し、創傷治癒を促進する有望な手段を提供する。
- 本レビューは、安定した軟組織界面を設計するための材料駆動型および生物学的戦略に関する最新の証拠を総合的に示し、歯科インプラントにおける重要な未充足ニーズに対処する、長期的な軟組織の健康に最適化されたインプラントシステムの開発のためのトランスレーショナルロードマップを提供している。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40505390
[quote_source]: Alexander R and Liu X. “Soft tissue integration around dental implants: A pressing priority.” Biomaterials 324, no. (2026): 123491.
監修者情報
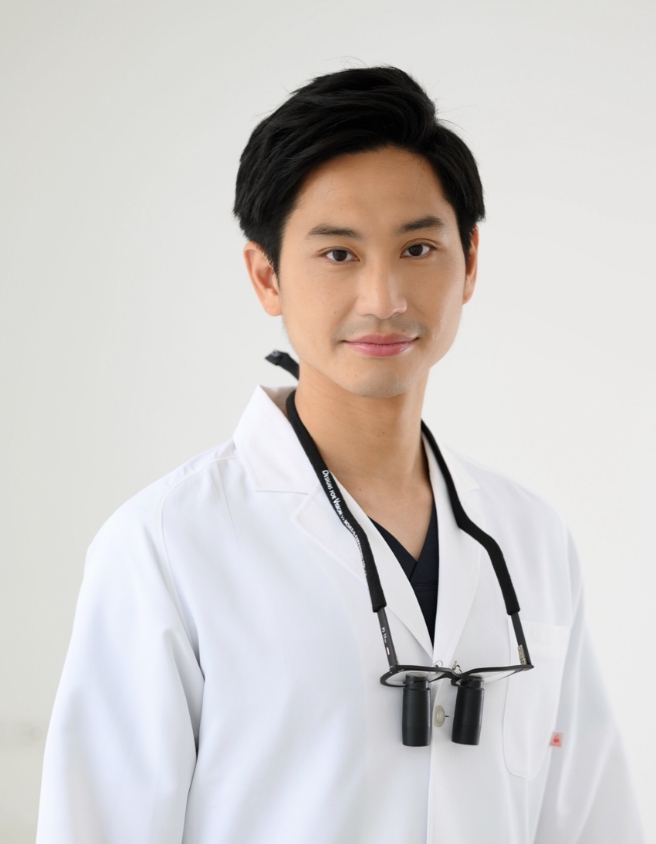
牧野歯科・矯正歯科 歯科医師
牧野 盛太郎Seitaro Makino
略歴
所属学会
- 日本口腔外科学会認定医
- 日本再生医療学会認定医
- 日本口腔外科学会
- 日本再生医療学会
- 日本顎顔面インプラント学会
- 日本口腔インプラント学会